2024年の政治、世界経済は波乱が続きます。それでも日本は景気拡大持続へ。それぞれの専門分野で、深く丁寧に将来を見通します。
2024年8月5日号 週刊「世界と日本」第2274号 より
一国平和主義からの覚醒
麗澤大学 客員教授
江崎 道朗 氏

《えざき みちお》
1962年、東京都生まれ。九州大学卒業後、国会議員政策スタッフなどを経て2016年夏から評論活動を開始。主な研究テーマは近現代史、外交・安全保障、インテリジェンスなど。産経新聞「正論」執筆メンバー。2023年、フジサンケイグループ第39回正論大賞を受賞。最新刊に『なぜこれを知らないと日本の未来が見抜けないのか』(KADOKAWA)。
尖閣・台湾有事の脅威が高まる中、日本は、国家戦略を大胆に変更してきた。
ではどのように国家戦略を変えてきたのか。これまでの「日本だけが平和であればいい」とする一国平和主義から、「同盟国、同志国と共にインド太平洋の平和と安全を守る」集団的自衛体制へと変えてきたのだ。
その転換を図ったのが第2次安倍晋三政権だった。2013年、安倍政権は戦後初めて日本独自の国家安全保障戦略を策定し、集団的自衛体制の構築に着手した。
国家安全保障戦略とはDiplomacy(外交)、Intelligence(インテリジェンス)、Military(軍事)、Economy(経済)の四つを組み合わせて日本の国益、平和を守ろうとする対外政略のことだ。
まず国家機密を守る法律として特定秘密保護法を制定し、同盟国、同志国と国家機密を共有できるようにした。
次にこれまでの孤立主義的な憲法解釈を一部変更したうえで平和安保法制を定め、「我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態」(重要影響事態)でも米軍等への支援を実施できるようにすることや、我が国の平和と安全が脅かされている状況下において米軍以外の外国軍隊に対しても支援ができるようにした。
こうした法整備を断行すると共に、日本はアメリカ以外の国、つまりオーストラリア、イギリス、フランス、カナダ、インドとも物品役務相互提供協定(ACSA)を結び、準軍事同盟のような関係を結んできた。
これは日本と他国との間で物資や役務を融通しあうための協定だ。軍同士で食料、燃料、弾薬、輸送、医療などを相互に提供できるようにするもので、安全保障・防衛協力を円滑に進め、連携の実効性を高める狙いがある。
こうした集団的自衛体制に関する法整備を進めながら日本は自由主義陣営全体で尖閣・沖縄を守る軍事訓練を繰り返している。
例えば2021年10月には沖縄沖で、日本、アメリカ、イギリス、オランダ、カナダ、ニュージーランドの各軍、具体的には空母3隻を含む6カ国・17隻の軍艦による共同訓練を実施している。
これは、中国に対して「日本に対して妙なことをするなら6カ国を敵に回すことになるのだがいいのか」と牽制したわけだ。
いくら言葉で「尖閣諸島を脅かすのはやめてください」と言っても聞いてくれる相手ではないからだ。
一方、アメリカも2022年、ジョー・バイデン民主党政権が国家安全保障戦略を改定し、同盟国、同志国との安全保障協力を強化する「統合抑止」という概念を打ち出した。中国などに対抗するためには、日本、韓国、フィリピンといった国々の協力が必要だということだ。
理由は幾つかあって、その一つは、中国の軍艦・戦闘機の数が、極東アジア地域に配備している米軍の軍艦・戦闘機の数倍あって、数では負けているという問題がある。
二つ目に、戦争は膨大な武器弾薬、燃料、食料、被服が必要になる。そうした膨大な物資をアメリカ本土から運ぶのは無理があり、台湾での紛争に対応するためには、物資補給などの面で日本などの協力が不可欠なのだ。
そこで日本はアメリカと物品役務相互提供協定(ACSA)を締結し、アメリカに「食料、水、宿泊、輸送、燃料・油脂・潤滑油、被服、通信業務、衛生業務(医療)、基地活動支援、保管業務、施設の利用、訓練業務、部品・構成品、修理・整備業務、空港・港湾業務」を提供する仕組みを整えた。
第2次安倍政権の国家戦略を更に拡大・強化したのが、岸田文雄政権だ。2022年12月、岸田政権は国家安全保障戦略を全面改定すると共に、5年間で43兆円の防衛関係費を閣議決定した。
この国家安全保障戦略の特徴は、次の5つの力を総合して集団的自衛体制をさらに強化しようとしている点だ。
第1が外交力だ。ロシアによるウクライナ侵略でも明らかなように、友好国、同志国をどれだけ持っているかが戦争の動向を左右する。よって日本も「地球儀を俯瞰する外交」と称して《多くの国と信頼関係を築き、我が国の立場への理解と支持を集める外交活動》を展開してきている。
第2が防衛力だ。それも防衛力に裏打ちされてこそ外交力は高まるとして《抜本的に強化される防衛力は、わが国に望ましい安全保障環境を能動的に創出するための外交の地歩を固めるものとなる》として、外交と防衛の連動を強めてきた。
第3が経済力だ。《経済力は、平和で安定した安全保障環境を実現するための政策の土台となる》。経済力があってこそ軍事力も強化できるのだ。
第4が技術力だ。《官民の高い技術力を、従来の考え方にとらわれず、安全保障分野に積極的に活用していく》ため経済安全保障推進法を制定すると共に、セキュリティクリアランス制度を導入し、自由主義陣営と連携して科学技術を発展させようとしているわけだ。
第5が情報力だ。《急速かつ複雑に変化する安全保障環境において、政府が的確な意思決定を行うには、質が高く時宜に適った情報収集・分析が不可欠である》。
この5つの力を使って第2次安倍政権以来、日本は集団的自衛体制を構築してきた。その結果、アメリカだけでなく、オーストラリア、イギリス、インド、カナダ、ドイツ、フランス、イタリア、ニュージーランド、フィリピン、NATOなどと安全保障関係を強化しつつある。
もちろん、アメリカとの安全保障関係も強化している。2024年4月、岸田首相が訪米してバイデン大統領と首脳会談を行い、米軍と自衛隊の相互運用性強化及び計画策定の強化を可能とするため日米それぞれの指揮・統制枠組みを向上させることで合意した。これは日米両国が本気になって戦うことを示さなければ、中国が戦争を仕掛けてくるかもしれないという危機感からだ。
日本は第2次安倍政権以来、中国、ロシア、北朝鮮などに対抗すべく自らの防衛力を抜本強化すると共に、安全保障面で同盟国、同志国を増やしてきた。
国家戦略レベルではもはや「一国平和主義」の時代は終わったのだが、国民の意識の方がどうやら追い付いていないように見えるのが気がかりだ。
2024年8月5日号 週刊「世界と日本」第2274号 より
『先輩・司馬遼太郎の魅力』
ジャーナリスト
千野 境子 氏

《ちの けいこ》
横浜市生まれ。1967年に早稲田大学卒業、産経新聞に入社。マニラ特派員、ニューヨーク支局長。外信部長、論説委員、シンガポール支局長などを経て2005年から08年まで論説委員長・特別記者。現在はフリーランスジャーナリスト。97年度ボーン上田記念国際記者賞を受賞。著書は『戦後国際秩序の終わり』(連合出版)ほか多数。近著に『江戸のジャーナリスト 葛飾北斎』(国土社)。
司馬遼太郎は大正12(1923)年8月7日、大阪市に生まれた。今月は生誕101年である。《その全作品から作家、歴史家、思想家、文明批評家と呼ばれることに異存はない。だが、私が兄事した三十余年間に刻んだ粗削りの司馬遼太郎像では、最後まで新聞記者であった》と追悼したのは、産経新聞で司馬と同時期を過ごし、東西両本社の編集局長を務めた青木彰である(『新聞記者 司馬遼太郎』所収)。共感する私も、だから先輩・司馬遼太郎の魅力にフォーカスし、司馬さんと呼んで稿を進めたい。
司馬さんは生涯に3つの新聞社で働いた。最初は新世界新聞という。復員して間もない昭和20年暮れ、故郷大阪の鶴橋界隈の闇市を歩いていて、電信柱の「記者募集」の貼り紙に目を止めたのが切っ掛けだった。
昭和21年6月には京都の新日本新聞に移り、宗教と大学を担当していたが、幹部の用紙横流しなどから新聞社は潰れてしまった。
司馬さんは担当が気に入っていたし、評価もされていた。さる人の口添えで昭和23年6月、産経新聞京都支局に横滑りした。
昭和27年7月に大阪本社地方部に異動するまで約4年、司馬さんは本来ベテラン記者が担当する「寺回り」を一度も外されなかった。約7年に及ぶ京都時代を、第42回直木賞受賞作『梟の城』を映画化した篠田正浩は《司馬さんの雌伏》期間と捉え、《元禄時代に武士の支配から遠く位置した都で公御侍として中世文学をわが物にし、不世出の芝居作者になった近松門左衛門の無名時代と重ねてきた》(前掲書)と書いている。
内勤である地方部から昭和28年5月に取材部門の文化部に移り、美術を担当。この頃には司馬さんの文章力は誰もが認めるところとなっていた。新聞記者・福田定一(本名)とともに作家・司馬遼太郎への助走も始まっていた。
昭和31年5月には応募作『ペルシャの幻術師』で講談社倶楽部賞を受賞し、同35年1月に『梟の城』で直木賞受賞へと続く。受賞直前に文化部長となった。そして翌36年3月、司馬さんは出版局次長を最後に、記者人生に別れを告げた。
産経新聞に入社した時、少なくとも10年は新聞記者をやろうと思っていたという。京都支局時代から13年、約束は果たしたということだろう。
さて、そこで先輩・司馬さんの魅力である。司馬さんはしばしば「人たらし」と言われる。「たらし」はどうもあまり綺麗な表現とは言い難い。それより私は、類まれなほどの人への優しさ、その背景にある包容力の大きさこそ、司馬さんの魅力ではないかと思う。
産経より作家時代の方がずっと長いのに、後輩への分け隔てない優しさは終生変わることがなかった。
私も産経新聞ニューヨーク支局長時代に一度お会いした。『週刊朝日』の連載『街道をゆく』の取材で来られた際に、食事の席に呼んで下さった。東京本社からその連絡があった時、恐縮しきりだったが、当日大勢の出席者がいる中、司馬さんの隣りに席を与えられた時は、感激するより私などが良いのだろうかと思った。優しい気遣いが心に沁み、後輩であることがちょっと誇らしい気がした。
せっかくの機会だし、お会いしたら少しでも珍しい話をと、ニューヨークのアメリカ先住民の話をお伝えしようと思っていた。だが結論を言えば、私の「出番」はなかった。近くの席にはニューヨーク在住で先住民に詳しいと紹介された方がいたし、司馬さん自身がそれを話題にされたからだ。
ああ、何と言うことと、天を仰ぐような気持だった。しかしとても楽しい一夜だった。司馬さんがリラックスし、愉快そうに語られる様子は、周囲を和ませた。「座談の名手」というのは本当だと感じ入った。
拙稿「司馬さんとの秘密」も司馬さんの優しさゆえの所産だと思う。平成7(1995)年1月1日付産経新聞の、司馬さんと国立民族学博物館顧問の梅棹忠夫氏との新春特別対談を読んでいて、司馬さんの発言にあっと息を呑んだ。
《そのころ、私は明石康さん(旧ユーゴ問題担当国連事務総長特別代表)の評伝を読みました。明石さんはカンボジアでの調整活動をしたとき、学生時代に聞いたーおそらく故泉靖一さんの講義でしょうー文化人類学が役に立ったといっています。異文化への尊敬という態度が相手に伝わったのでしょう」。この後、司馬さんは青年・梅棹の内蒙古でのフィールドワークに触れ、対談は自然と民族と文明という本題に入っていった。
私があっと思ったのは、評伝の著者は私だからだ。前年10月に出版した『明石康 国連に生きる』を、司馬さんがお忙しいことは重々承知していたが、ニューヨークの一期一会のご縁にとお送りした。
すぐに感想を記された直筆の葉書が届いたのに驚いたが、さらにお正月の特別対談で言及までして下さるとは。しかもその事実を知るのは、司馬さんと私しかいない。大きなお年玉を頂いたような気がした。
後に司馬遼太郎記念館会誌『遼』に寄稿した際(2013年秋季号)に、私は迷うことなく見出しを「司馬さんとの秘密」としたのだった。
葉書の文面にも、司馬さんらしい優しさとユーモアが溢れていた。素晴らしい本でしたと過分なお褒めの言葉に加えて、文面の最後に(千野さんの小さな写真、カラーだともっとよかったのにね)とあり、思わずクスッと笑ってしまった。1度会っただけの一記者に、こんなにも心のこもった言葉をさり気なく注ぐ司馬さんの優しさは、並外れている。
晩年、司馬さんはある会合で、同席した田中直毅氏の質問から、こんな会話になった。
「司馬さんは、もし生まれかわったとしたら、やっぱり新聞記者になられますか」「そうやねえ、なると思いますなあ」「どこの新聞に入られますか」「うーん、やっぱり産経でしょう。青木君、キミはどうや」「ボクも産経だと思いますね」(前掲書)。
ここに司馬さんの魅力が凝縮されている。甘いねと言われそうだが、後輩記者としては嬉しい。
2024年7月15日号 週刊「世界と日本」第2273号 より
混迷・分断の世界情勢「潔癖症の時代」を生きる
日本大学 危機管理学部教授
先﨑 彰容 氏

《せんざき あきなか》
1975年東京都生まれ。専門は近代日本思想史・日本倫理思想史。東京大学文学部倫理学科卒業。東北大学大学院博士課程修了後、フランス社会科学高等研究院に留学。著書に『未完の西郷隆盛』、『維新と敗戦』、『バッシング論』、『国家の尊厳』など。
いつの時代もそうなのかもしれないが、最近、特に「怒り分断」が私たちを取り巻いている気がする。
露ウ戦争と中東激変は、欧米と反欧米の対立軸を鮮明化している。六月十一日、ロシア西部の都市ニジニ・ノブゴロドでBRICS外相会議が開催された。BRICSとはロシア、ブラジル、インド、中国、南アフリカによって二〇〇六年に設立された経済圏であり、その後、エジプト、イランなど中東諸国も参加を表明し、規模を拡大している。そのわずか一週間前、バイデン大統領とゼレンスキ—大統領の姿はパリにあった。第二次世界大戦のノルマンディー上陸作戦八〇周年記念式典に参加し、対ロシア連帯を確認したのである。G7の一員であるわが日本にとって、自由と民主主義に基づく豊かな資本主義社会は、自明の正義に思える。だが世界が直面しているのは、その正義が「自明」でもなんでもないという事実なのだ。
とりわけ筆者が注目したいのは、BRICSに、ロシアや中国などに加え、中東諸国が加わっていることである。中東は複雑だ。イランが反米的価値観の国であることは自明としても、エジプトなど近代化を一定程度受け入れた国の方に注目したい。近代化した中東をみて、私たちは「こちら側」に来たと思いがちである。だが実際は、国内に大きな貧富の格差を生み出した結果、経済的ゆたかさの恩恵にあずかれない多くの国民にとって、自国の欧米化は違和感しかもたらさない。違和感とは、実際の金銭的不如意よりも、むしろ自分が蔑ろにされているという感覚である。すなわち「尊厳」が傷つけられているのだ。社会の片隅で貧しく暮らす人たちからみれば、近代化=欧米化とは、一部の者たちが浴びるほど喰い、夜更けまで遊び、男女が堕落した関係に溺れる社会にみえる。つまり欧米化は人間の堕落とおなじである。こうした気分を抱えて、都会でその日暮らしをし、孤立した個人に「宗教的なもの」が魅惑的に思えるのは当然である。かつて、この国の人びとはもっと誠実であり、品行方正であり、隣人を気遣った。男女には慎みがあり、宗教的にも敬虔であった。にもかかわらず、アメリカがこの地を席巻して以降、堕落の一途をたどっているのではないか—表面上、欧米化した国内に反欧米の空気が漲りつつある。中東国民は、それぞれが置かれた立場によって、「怒りと分断」を深めているのだ。
より身近な事例に眼を転じてみよう。日本国内でも、LGBT法案可決の是非にはじまり、選択的夫婦別姓をめぐる左右の対立、補欠選挙における異常な選挙妨害など、「怒りと分断」は先鋭化している。一つひとつの事柄に、筆者なりの意見も立場もあるが、ここで指摘しておきたいのは「思想的経緯」である。言いかえれば、眼の前の事象は、ここ数十年の歴史を俯瞰しない限り、よく理解できないということだ。どうして現在のような状況が生まれているのか、一九六〇年代にまで遡ってみてみよう。
「一九六八年」が、世界的規模で若者たちの反乱が起きた年であることは有名である。第二次世界大戦が終わり、東西冷戦の最中ではあったが、資本主義はそれなりの成熟段階を迎えていた。従来の左翼運動に代わり、「新左翼」と呼ばれる思想が登場したのが、この時期である。では何が新しかったのか。従来の左翼は、共産主義に典型的なように、階級闘争を中心としていた。ブルジョアとプロレタリアートとは、要するに経済的強者と弱者のことであり、弱者による政権奪取こそが革命の大義だった。労働組合運動は、社会的保護と富の再分配を要求したし、共産主義陣営こそユートピアに他ならなかった。それは資本主義の止揚や国家の革命による解体を目指す「大きな物語」を描くことに特徴があった。
一方の新左翼の新しさは、政治の主題を、より個別の問題へと絞っていった点にある。「大きな物語」に代わり、新左翼が訴えたのは個人の「尊厳」の尊重だった。黒人差別、フェミニズムなどの女性の権利要求、性的少数者の権利擁護などがそれである。特徴は、彼らが不当だと主張するものが、生得的な特徴だという点にある。肌の色や女性であることは後天的ではないし、性自認も同じである。男性には決してわからない、あるいは当時者以外には理解しがたい特徴を、シモーヌ・ド・ボーヴォワールは「生きられた経験」と名づけ、左翼運動の支柱に据えた。私たちの社会には、夥しい数の不正が存在する。それを一つずつ論い、糾弾し、虐げられてきた側の権利を貫徹することが目指される。共産主義の「大きな物語」が資本主義や国家など、政治経済システム全体の革命を主張する運動だったのにたいし、新左翼は、資本主義の勝利を前提したうえで、個別細分化した反権力闘争を行うことになったのだ。
その最たる一例を挙げよう。あるフェミニストによれば、女性に対する男性の性行為は、「レイプと性交は区別できない」のだという。性行為それ自体が、男性中心主義なのであって、批判されるべきなのである。
この主張にこそ、現代社会を読み解くヒントがあると思う。すなわち、現代社会は、絶対的正義の貫徹を目指すあまりに、微細な差別や差異を許さない「不寛容な社会」になっている。少しでも「尊厳」を傷つけられると、瞬間的に「怒り」が沸騰し、糾弾運動がはじまる。正義は純粋化し、社会はグレーゾーンをなくし、誰もが言葉を発しにくくなる。生きにくい社会を生み出しているのだ。
例えば衛生を求めて、三回手を洗うとき、人は正常であろう。だが百回洗えば、それは潔癖症という病になる。そして現代社会は、完全に「潔癖症の時代」になっているのではないか。余りに行き過ぎた正義感が、「怒りと分断」を社会に蔓延させているのだ。三回程度の手洗いが無難だという基準は、結局、「常識」という名の秩序にしか根拠がない。この「何となく正しい」という感覚、グレーゾーンこそ、今、最も失われている感覚なのである。
2024年7月15日号 週刊「世界と日本」第2273号 より
欧州へ進出する日本メーカー
欧州鉄道フォトライター
(チェコ共和国プラハ在住)
橋爪 智之 氏

《はしづめ ともゆき》
1973年東京都生まれ。欧州鉄道フォトライター。日本旅行作家協会(JTWO)会員。主な寄稿先はダイヤモンド・ビック社、鉄道ジャーナル社(連載中)など。
現代社会に於いて、人や物の流れに無くてはならない存在となった鉄道。1802年、英国の技師リチャード・トレヴィシックによって発明された蒸気機関車は、ジョージ・スティーブンソンの手でより実用的なものへと改良され、1825年9月には初の公共鉄道として営業を開始。以来、まもなく200年という長い歴史を刻むことになる。英国はいわば鉄道発祥の地であり、日本にはその英国から1872年に直接輸入され、新橋~横浜間で営業を開始した。鉄道は瞬く間に輸送手段の中心的存在となり、航空機や自家用車という競合が誕生した後も、交通機関の主役として現在も世界中で活用されている。
日本は、欧米諸国からはかなり遅れて鉄道が導入されたが、その後の進化、成長ぶりは言うに及ばず。世界初の高速鉄道として、1964年に誕生した新幹線は、とりわけ他の交通機関に押され、衰退の一途を辿っていた「鉄道先進国」たる欧州各国にショックにも近い影響を与え、後のTGVやICEといった高速列車の誕生に繋がった。新幹線が誕生しなければ、今の世界的な鉄道の発展は無かったかもしれない。
世界へ大きな影響を与えた日本だが、島国の中で独自の進化を遂げてきた日本の鉄道は、世界ではかなり特殊な存在であることをご存じだろうか。英国から鉄道が輸入された当時、建設費の抑制や、起伏の多い地形に適した規格ということで、線路幅や車体は欧米の標準的な大きさよりは小ぶりとなっている。
その一方で、東京や大阪などの大都市圏においては、人口の増加によって朝夕の通勤・通学ラッシュが深刻な問題となり、鉄道会社は輸送力増強へ設備投資を行い、今では10両以上も連結された列車が数分おきに発着を繰り返すというのが日常的な光景となっている。このような高頻度運転も特殊だが、それを以てしても積み残しが出るほどの利用客数も、他国から見ればかなり特殊だ。
このように日本という島国の中で、地域の特性に合わせる形で独自の進化を遂げた日本の鉄道は、他に類を見ない特殊な鉄道となった。そのこと自体は悪くないが、言い換えると日本の技術は「ガラパゴス化」したもので、いくら高性能・高品質でも、そのまま海外へ持ち込んでも見向きもされない。もっとも、国内メーカーは日本の鉄道会社への需要だけで十分利益が生み出せており、積極的に海外へ進出を図る理由はなかったから、無理に他国の規格へ合わせる必要はなかった。
もちろん、各メーカーはまったく海外へ目を向けていなかったわけではない。アメリカ主要都市向けの地下鉄車両は、かなり以前から日本のメーカーが受注しており、現地に組み立て工場があるメーカーもある。アジア向けでも、日本の車両を納入した実績はある。だがいずれも、全体の売り上げから見れば小規模なもので、相変わらず国内の需要に頼る必要があった。
また輸出先に、ヨーロッパの国々は含まれていなかった。日本と並ぶ鉄道先進地域であるヨーロッパ圏には、鉄道車両メーカーが数多くあり、日本と異なる現地のノウハウを多く持っている強みもあるため、そこへ日本のメーカーが割って入ることは非常に困難で、リスクをわざわざ負う理由もなかった。
しかし、その困難へあえて立ち向かったメーカーがあった。日立製作所だ。
もちろん、最初から順風満帆というわけではなかった。常識的に考えて、長年の付き合いがある地元メーカーを捨て、新興勢力に身を委ねようというリスクを取るには、各国の鉄道会社にとってもそれ相応の覚悟と勇気が必要だ。日立が最初に進出を決めた先は、鉄道発祥の国英国だった。英国は、ヨーロッパという地域圏にありながら、日本と同じ島国で、ドーバー海峡に海底トンネルが完成するまでは、大陸側とは線路も繋がっていなかった。車両規格も、英国だけは特殊で、大陸側の規格とは異なっており、条件としては地元欧州メーカーとイーブンであった。また英国は、機関車牽引の列車がほとんど姿を消し、日本と同じ電車や気動車が多く活躍していることも、市場へ割って入る隙があったと言える。
結果、日立は高速新線HS1を通り、ロンドンとドーバーを結ぶ最高速度225㎞/hの近郊列車「ジャヴェリン」の受注を獲得する。日本のメーカーとして初めて、欧州地域におけるまとまった数の車両を受注するに至った。それと同時に、1872年に英国から技術や車両を輸入し、発展してきた日本の鉄道が、その鉄道発祥の地である英国へ、逆に車両を輸出するという立場となった歴史的な快挙でもあった。ジャヴェリンは非常に好評で、後に制御装置の更新案件や英国北部の近郊列車なども受注、ついには都市間特急インターシティの車両置き換えという大型案件の受注へと繋がった。受注は総計800両以上に達し、英国内における日立ブランドを不動のものとした。
一方で日立は、敷設からメンテナンスまで長期的な収益が見込める信号システムの技術を欲しており、欧州信号大手だったイタリアのアンサルドSTSを買収、その際に車両メーカーのアンサルドブレダも一緒に買収しており、大陸側にも拠点を設けることに成功した。ブレクジットの影響で、先行きが見えなかった英国市場を思えば、リスクを分散することに成功したと言える。
鉄道メーカーの数ある事業の中で、目に見える車両製造は消費者にも訴えかけやすい花形事業であるが、収益面で言えば信号・通信系事業の方が安定している。2024年に入り、日立は信号・通信大手のタレス社を買収、同分野の最大手に上り詰めた。
日立の躍進にばかり注目が集まっているが、前述の通り鉄道事業は車両製造だけではない。三菱電機は、制御装置やエアコンなど、装置単体を多くの欧州鉄道メーカーへ納入しており、その売り上げ規模は日立製作所をも凌ぐほどであった。国内景気が不透明な中、こうしたパーツ供給という部分では、日本の鉄道メーカーも欧州市場へ参入する可能性を秘めていると言えるのではないだろうか。
2024年7月1日号 週刊「世界と日本」第2272号 より
派閥解消で自民党はどうなるのか
政治評論家
伊藤 達美 氏

《いとう たつみ》
1952年生まれ。政治評論家 (政治評論 メディア批評)。講談社などの取材記者を経て、独立。政界取材30余年。中曾根内閣時代、総理官邸が靖国神社に対し、“A級戦犯”とされた英霊の合祀を取り下げるよう圧力をかけた問題を描いた「東條家の言い分」は靖国神社公式参拝論争に一石を投じた。著作多数、夕刊フジ「ニュース裏表」(木曜日発売)、自由民主「メディア短評」の執筆メンバー。ラジオ日本報道部客員解説委員。
岸田文雄首相は、派閥政治資金パーティーの収支報告書未記載事件を契機に、自ら率いてきた岸田派を率先して解散し、安倍派、二階派、森山派もこれに続いた。
さらに茂木派も解散に踏み切り、残るは麻生派だけになった。今や自民党のほぼ全員が無派閥議員だ。
しかし、派閥は元来、総裁選に対応するために生まれたものだ。総裁選が存続する限り、これまでのような形態であるかどうかはともかく、「派閥的」な議員集団は必然的に生ずる。行き過ぎを改めるのは当然としても、派閥そのものを否定や禁止することはできないのではないか。
自民党以前の保守政党の総裁は、基本的に話し合いによって選ばれていた。これに対して自民党は立党時の有力者であった緒方竹虎氏の強い主張で「公選」によって総裁を選ぶことを原則とした。立党の際、初代総裁は翌年4月の総裁選で選出することとし、それまでの間、4人の総裁代行委員で総裁の職務を代行することにしたのはそのためだ。
最初の総裁選は有力候補の緒方氏が急逝したため、当時首相だった鳩山一郎氏の信任投票的な総裁選となったが、鳩山首相の後継を選ぶ1956年12月の総裁選は激しい選挙戦が繰り広げられた。最終的に石橋湛山氏と岸信介氏との決選投票となり、わずか7票差で石橋氏が後継総裁に就任した。
この時、投票によって総裁を決定する意味が強く印象付けられたのかもしれない。池田勇人氏を総裁にすることを目的に「宏池会」が結成されたのは、この翌年の1957年6月のことだ。
そして、岸首相の後任を選ぶ1960年7月の総裁選で、池田氏が決選投票の末に石井光次郎氏を破り第4代自民党総裁に就任した。以後、総裁選が定着するに従い、総裁を目指す政治家は派閥を作り、同志との関係を深め、メンバー拡大にいそしむようになった。
政治改革論議が盛んだったころ、派閥は中選挙区制に起因する説が有力だった。したがって、小選挙区制になれば派閥の必要性は薄れていくと考えられていた。しかし、それは誤りだった。そのことは、かつて派閥解消を唱えていた石破茂氏が総裁選にチャレンジするにあたって、自らの派閥を作ったことでもわかる。
1989年に自民党が決定した「政治改革大綱」で派閥解消を決めたにもかかわらず、「守られていないのはおかしい」との主張があるが、前提に誤りがある以上、想定通りにならないのは当然だ。それに、「大綱」との齟齬をきたしているのは派閥解消だけではない。「大綱」との整合性を問題視するなら、「小選挙区制の導入」によって、「国民本位、政策本位の政治を実現する」との根本目的が果たせているのかどうかを検証すべきではないかと思う。
かつて派閥は党の統制を乱す要因ととらえられていた。いわゆる「三角大福」の時代までは激しい派閥抗争がしばしば発生し、派閥解消が党改革のテーマとして度々議論された。
しかし、その後、派閥抗争が落ち着きをみせると、派閥は党運営の潤滑剤としての役割を担うようになっていった。
例えば、週一回開く定例の派閥総会では、執行部や国会方針の説明が行われ、党の方針を派閥単位で共有する。また、個々の議員の要望や意見が同じ派閥の副幹事長などを通じて執行部に伝えられる場面も少なくない。派閥は自民党の「風通しの良い党風」の一翼を担っていたと言える。
もっと大きな視点で考えれば、複数の派閥の存在していることによって、党執行部の専横をけん制し、党の民主的運営を確保するうえで大きな役割を果たしているともいえる。それは執行部の権限が強大化しがちな小選挙区制の導入によって、より重要になってきた側面もある。
一方、既成の派閥が硬直化していたのも事実だ。総裁選対応のための派閥だったにもかかわらず、そのほとんどが総裁候補を持たず、新たなリーダーを選ぶ総裁選に対応できなくなっていた。現在の岸田総裁を選出した2021年の総裁選でも、派閥としてまとまって行動できたのは、領袖が立候補した岸田派だけだった。その他の派閥はバラバラな対応を余儀なくされた。その意味で、早晩、派閥再編は不可避だったといえる。
今年9月には総裁選が予定されている。こうしたなか、総裁選立候補を志す議員の下に議員集団が形成されるのは自然の流れだ。しかし、当面は、次の総裁選に対応するための活動にとどまるだろう。その後も継続的に活動を続けて「派閥化」するかどうかは、その総裁候補の将来性次第だ。
総裁選には、これまでよりも多く候補者が立候補するのではないかと予想する。これまで派閥が推薦する候補以外への推薦人に名を連ねることは基本的になかったが、派閥のくびきが解き放たれたことで推薦人を確保が容易になるからだ。当選可能性のない候補者が乱立することが良いとは思わないが、自民党の新たな胎動を感じさせるニューリーダーの出現を望むのは筆者だけではないだろう。
ただし、ニューリーダーの下で派閥が再編され、一定の形に収斂するまでには相当な時間がかかることは織り込んでおかなければならない。
問題は、新しい形ができるまでの間に、無派閥化に伴うデメリットが表面化する可能性があることだ。自民党は無派閥化の影響を軽く考えるべきではないと思う。
特に、「党内の潤滑油」的な役割を果たしてきた派閥がなくなったことで、執行部のガバナンスの低下は避けられないのではないか。すでに今国会中、そうした兆候が表れている。単に総裁、幹事長の指導力不足というより、派閥解散による構造的な変化と見るべきだろう。
政権与党が「まとまりの悪い政党」になったらどうなるか。これまでは自民党の「一強政治」が批判されてきたが、これからは「全弱政治」が出現することになるかもしれない。はたして自民党は「ニューリーダーの時代」を迎えられるのか。乗り越えられなければ、自民党は「流動化」を超えて「液状化」の様相を呈することになる。
いずれにせよ、日本政治は当分の間、「生みの苦しみ」に付き合わざるを得ないことになるのではないか。
2024年6月3・17日号 週刊「世界と日本」第2270・2271号 より
政権は沈没寸前「危険水域」続く
問われる岸田首相の改憲の本気度
評論家 ノンフィクション作家
塩田 潮 氏

《しおた うしお》
1946年高知県生まれ。慶大法卒。雑誌編集者、月刊『文藝春秋』記者などを経て独立。『霞が関が震えた日』で講談社ノンフィクション賞受賞。『大いなる影法師』、『昭和の教祖 安岡正篤』、『日本国憲法をつくった男 宰相幣原喜重郎』、『憲法政戦』、『密談の戦後史』、『内閣総理大臣の沖縄問題』、『危機の権力』、『解剖 日本維新の会』、『大阪政治攻防50年』。近著に『安全保障の戦後政治史』など著書多数。
6月23日、通常国会が会期末を迎える。岸田文雄内閣の支持率は2012年12月の自民党政権復活後の最低の水準で、政権は沈没寸前の危機的状況だ。
不人気はもちろん自民党の「派閥とカネ」が最大の原因だが、岸田首相は内政、外交とも、特筆すべき実績や成果が乏しく、国民から賞味期限切れと見られている点も大きい。
その中で、政権獲得となった21年9月の自民党総裁選以来、ぶれずに唱え続けている主張がある。「在任中の憲法改正実現」だ。
岸田改憲路線については1年前、月刊『世界と日本』(23年5月1日合併号)の拙文で詳述したが、首相はその後、24年1月、国会での施政方針演説で、「総裁任期中の改憲実現との思いに変わりはなく」と明言した。5月3日の憲法記念日にも、「先送りできない重要な課題」と訴えた。
「総裁任期中」とは1期目の任期満了までと見るべきだろう。だが、政権は大苦境で改憲どころではない。もし苦境を脱したとしても、残り3カ月余で、実現は絶望的である。
改憲は衆参での総議員の3分の2以上の賛成による国会発議と、国民投票での過半数の賛成が必要だ(憲法96条)。国会の積極的改憲支持勢力は自民党、日本維新の会、国民民主党、衆議院の有志の会の4会派である。
5月末の合計議員数は、衆議院が「3分の2」の3超の314、参議院は19不足の147だ。消極的改憲勢力の公明党(参議院27)の賛成がなければ、発議は成立しない。
「数の壁」だけでなく、「発議案の壁」も厚い。衆参の憲法審査会は継続審議中だが、発議案の原案となる条文案は、作成の段階に至っていない。
ほかに「時間の壁」も高い。仮に今後、改憲原案がまとまって、「数の壁」も突破して発議が成立したとしても、国民投票まで60〜180日が必要だ(日本国憲法の改正手続に関する法律2条)。
9月30日の自民党総裁任期満了までに国民投票を実施するには、最短で8月上旬の国会発議が条件となる。それまでに発議が成立する確率はゼロに近い。
一方、5月2〜3日発表の世論調査では、朝日新聞「憲法を変える必要がある」53%、読売新聞「憲法を改正する方がいい」63%、共同通信「改憲の必要性・ある」(どちらかといえばを含む)75%であった。今や国民の過半数が改憲を支持・容認している。
多くの国民が望むテーマだから、岸田首相も「総裁任期中の改憲実現」「先送りできない重要な課題」と説き続けているということなら、理解できる。
ところが、就任後の憲法問題への取り組みを見ると、空念仏の印象が強い。首相としてではなく、自民党総裁の立場で各党に党首会談を呼びかけるなど、リーダーシップを示すことは可能なのに、何の動きもなかった。
「口舌の徒」という批判もある。実際は建前と本音の使い分けが岸田流と思われる。
「総裁任期中の改憲実現」を言い続ける本音は以下の5つが目的で、「一石五鳥」の思惑があると見る。
第1は政権獲得時の安倍晋三元首相の支持の取り付けだ。「改憲挑戦と支持確約」の密約があったのでは、という見方は根強い。
第2は長期政権戦略も考えられる。実現まで長期を要する大計画を達成目標に掲げ、挑み続ける。「実現まで政権担当を」と訴えて支持を得れば、結果的に長期政権に、という政権維持の妙手だ。
佐藤栄作元首相の沖縄返還、中曽根康弘元首相の3公社改革、小泉純一郎元首相の郵政民営化という先例がある。改憲を達成目標とする手があると岸田首相も気づいたのか。
第3は積極的改憲勢力の野党の抱き込みである。「自民1強」が崩れた場合、野党を取り込む武器として、足並みがそろう「改憲」を活用する。その布石をという計略も働く。
第4は政権の遺産作りを視野に入れているかもしれない。岸田首相はすでに過去37年の19人の首相で第3位の在任記録を築いているが、歴史に残る政治的遺産は見当たらないのが弱点とされる。それなら改憲実現を遺産の対象に、と考えたとしても不思議ではない。
第5は衆議院解散との関係だ。総裁再選を願う岸田首相は、次期総裁選前の衆院選実施・総選挙克服が再選の近道と見定め、何度も機会をうかがってきたが、すべて不発に終わった。開会中の今国会末期の解散も企図したが、6月3日の時点で「見送り」がほぼ確実という状況となった。
度重なる解散不発は支持率低迷が不発の主因だったが、「解散の大義」の不在が響いた。国民の信を問う重要テーマがなく、政権延命狙いの解散と国民に見透かされた。今後、総裁選前の衆院選実施は絶望視されているが、もし機会があれば、争点として「改憲」を持ち出す可能性もある。
「在任中の改憲」の本音が上記の「一石五鳥」だとすれば、岸田首相の改憲の本気度が問題になる。岸田首相は17年8月に安倍政権で自民党政調会長に起用されるまでは護憲派だった。改憲派に転じたのは、将来の政権獲得を視野に安倍氏との連携を狙ったからだ。
他方、旧宏池会会長の宮沢喜一元首相の影を引きずり、今も「護憲派のしっぽ」を残しているのでは、と疑う人もいる。岸田首相は就任前、筆者の取材に答えて「徹底した現実主義を貫くのが宏池会の伝統。時代の変化に応じて徹底した現実主義で」と強調した。
国民の多数が改憲を容認する時代だ。民意の変化に応じて現実主義的対応で改憲を叫ぶのであれば、施行後77年、制定時からの不備や欠陥だけでなく、社会や世界の変革への不適応が目立つ憲法の見直しにも、現実主義的対応が欠かせない。
不在の緊急事態条項の新設、「地方自治」の章の充実などのほかに、デジタル時代の人権保障、サイバー攻撃に対する防御をめぐる「憲法の障壁」も今や喫緊の重要な検討項目だ。「改憲実現」は実は自身の政権維持のための現実主義的対応という計算があるなら、即刻、降板し、真剣に憲法問題を考える本気度で本物のリーダーと交代すべきである。
2024年4月1日 週刊「世界と日本」第2266号 より
「福澤とジャーナリズム-脱亜論への道」
拓殖大学 顧問
渡辺 利夫 氏

《わたなべ としお》
1939年6月甲府市生まれ。慶応義塾大学、同大学院修了。経済学博士。筑波大学教授、東京工業大学教授、拓殖大学総長を経て現職。オイスカ会長。外務大臣表彰。正論大賞。著書は『成長のアジア 停滞のアジア』(吉野作造賞)、『開発経済学』(大平正芳記念賞)、『西太平洋の時代』(アジア太平洋賞大賞)、『神経症の時代』(開高健賞正賞)、『台湾を築いた明治の日本人』『後藤新平の台湾—人類もまた生物の一つなり』など多数。
日本の新聞ジャーナリズムは、明治の前半期、自由民権運動の広がりとともに勃興期を迎えた。しかし、ほとんどの新聞が政党色を帯び、政党機関紙のごときものであった。しかし、その中にあって、福澤諭吉の創刊した『時事新報』は、いかにも在野の言論人・福澤のものらしく、「不偏不党」を編集の主眼とし、執筆・経営陣も福澤を中心として中上川彦次郎、牛場卓蔵、石河幹明らの門下生の俊秀に支えられて刊行がつづけられた。
『時事新報』について調べてみると、大抵がこのように解説されている。間違いではないが、筆者にはこの新聞の主眼が「不偏不党」であったとはにわかには信じられない。掲載された論説のほとんどは福澤自身の手になる。その圧倒的多数は朝鮮問題に焦点が当てられ、それらは朝鮮の政情に対する福澤の憤懣(ふんまん)をあらわにしたものであり、朝鮮開化派に対する支援の必要性を訴えたものばかりである。ただ筆を執っていたばかりではない。
福澤は門下生の牛場卓蔵と井上角五郎の二人を朝鮮に派し、朝鮮政府に対し彼らを諸改革の顧問にするよう要求した。牛場への激励文「牛場卓蔵君朝鮮へ行く」が『時事新報』(明治11年1月11〜13日付)に掲載された。朝鮮改革への福澤の固い決意と、この決意を牛場に託した福澤の深々とした思いがつづられている。
「行(ゆき)て彼の開進の率先者と為(な)り、その士人の俊英なる者を友としてその頑陋(がんろう)なる者を説き、之(これ)を激して之を怒らしめず、之を諭(さと)して之を辱(はずか)しめず、君の平生処世の技倆と学問の実力を以(もつ)て、懇々(こんこん)之に近づき諄々(じゅんじゅん)之を教ゆることあらば、之を開明に入るゝ亦(また)難きに非ず。或はその際に事の挙(こぞ)らずして堪え難きこともあらんと雖(いえ)ども、我蘭学の先人が百余年前に辛苦したる有様を想えば驚くに足らず。・・・・・君も亦朝鮮国に在て全く私心を去り、猥(みだり)に彼の政事に喙(くちばし)を容(い)れず、猥に彼の習慣を壌(ゆず)るを求めずして、唯一貫の目的は君の平生学び得たる洋学の旨を伝て、彼の上流の士人をして自から発明せしむるに在るのみ」
福澤がどうしてここまで朝鮮問題に深い関心を寄せたのか、門下の言論人の竹越與三郎はあるエッセイのなかで福澤は朝鮮に恋をしていたと述べている。
「渠(かれ)が胸中の政治的熱気は、決して初より抑ゆるべからずして、遂に朝鮮経略の上に澆(そそ)がれたり。実に朝鮮は渠が最初の政治的恋愛にして、最後の政治的恋愛なりと云うを得べし」
当時、深刻の度を深めていた李朝末期の朝鮮の政治改革を求める開化派官僚が、福澤の教えを乞いに三田の慶應義塾を次々と訪れた。福澤は、自分の過去の苦悩を彼らの中に見出し、少なくとも自分を頼ってくる朝鮮人には、救いの手を差し伸べることは自分の責(せめ)だと感じた。福澤は、かつて幕臣であったものの、明治維新という大業には参加することなく、傍観者としてやり過ごした。このことを深く悔やんでいたのにちがいない。そのために、みずからの思想の新しい実現の場をどこかに求めており、その場が朝鮮となったのであろうと筆者はみている。

開化派が朝鮮で、後に甲申事変と呼ばれるクーデターを起こし、これは結局のところ無惨な失敗に終わったものの、開化派への福澤の支援は生半(なまなか)なものではなかった。福澤は朝鮮に派遣されていた井上角五郎、開化派のリーダー金玉均との三者間でモールス信号で連絡し合い、またクーデターに備えて数十口の日本刀を井上のもとに送ったという記述がある。
甲申事変は守旧派と清国からの援軍の反撃によって「三日天下」に終わった。甲申事変の首謀者は朝鮮政府によって残酷刑に処せられた。このことを伝え聞いた福澤の心は憤怒(ふんぬ)に満たされ、『時事新報』(明治18年2月23日、28日付)の論説として「朝鮮獨立党の處刑」を掲載。「人間娑婆世界の地獄」が京城に出現、朝鮮は野蛮などというレベルをはるかに超えた「妖魔悪鬼の國」と化し、その残忍なありさまは「寒心戦慄」するものだと朝鮮を難じた。さらに、福澤はこの処刑に直接手を下した者は確かに朝鮮守旧派官僚だが、首謀者の処刑を指揮した者はまぎれもなく清国官僚だと主張したのである。
「朝鮮獨立党の處刑」を書いた日から20日後の『時事新報』において、福澤が激憤の感情をそのままに一気に認めたものが、かの「脱亜論」である。この「脱亜論」で語られる「支那朝鮮」こそ現在の東アジアに他ならない。日本を取り巻く東アジア情勢のきわどさをいかにもと思わせる筆致で描写した論説が「脱亜論」である。言葉遣いの激越さに惑わされることなく、福澤「脱亜論」の真意をいまこそ深く読み取りたいと思うのである。
2024年4月1日 週刊「世界と日本」第2266号 より
寺田寅彦「天災と国防」の警鐘から学ぶ
拓殖大学 地方政治行政研究所
特任教授
濱口 和久 氏

《はまぐち かずひさ》
1968年熊本県生まれ。防衛大学校材料物性工学科卒。名古屋大学大学院環境学研究科博士後期課程単位取得満期退学。陸上自衛隊、栃木市首席政策監などを経て現職。東日本国際大学健康社会戦略研究所客員教授、日本大学法学部公共政策学科非常勤講師も務める。著書に『リスク大国 日本 国防・感染症・災害』(グッドブックス)ほか。
日本にとって令和6年は元旦から災禍が襲う事態となった。石川県で最大震度7を記録する能登半島地震が発生した。日本人の都合に関係なく甚大な被害をもたらす地震が日本列島のどこで発生してもおかしくないということを改めて証明した格好だ。
震度7クラスの地震は平成7(1995)年に発生した兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)から能登半島地震までの29年間に7回発生している。約4年に1回の間隔で日本列島のどこかで発生している。今後もどこで震度7クラスの地震が発生してもおかしくない。日本人は地震に対する備えを片時もおろそかにするべきではない。
首都直下地震や南海トラフ巨大地震の発生も不安要因だ。近年は気候変動が原因と思われる台風の巨大化や豪雨の多発化により甚大な風水害がたびたび発生している。
また、新型コロナウイスの感染は終息したとはいえ、新たな感染症が発生する可能性もある。国民保護法が想定するような武力攻撃事態も心配だ。
「科学的国防の常備軍」とは
地球物理学者の寺田寅彦が昭和9(1934)年11月、雑誌『経済往来』に寄稿した「天災と国防」に次のような記述がある。
「日本は、(中略)気象学的地球物理学的にもきわめて特殊な環境の支配を受けているために、その結果として特殊な天変地異に絶えず脅かされなければならない運命のもとにおかれていることを1日も忘れてはならないはずである。
日本のような特殊な天然の敵を四面に控えた国では、もう一つ科学的国防の常備軍を設け、日常の研究と訓練によって非常時に備えるのが当然ではないかと思われる」
寺田が「特殊な天変地異に絶えず脅かされなければならない運命のもとにおかれている」と書いているように、日本は約1500年間に死者1000人以上の大災害を99回経験している。日本の25倍の国土面積を持つ米国は、建国から今日までの約250年間で3回だけだ。先進国のなかで日本の99回を超える国家は存在しない。ちなみに、イギリス、フランス、ドイツは1回もない。日本人は大災害リスクから逃げられない(日本人は大災害と隣り合わせで暮らしている)ことがこの数字からも一目瞭然にわかる。
「科学的国防の常備軍」については、人それぞれに様々な解釈があるだろうが、現代で言えば、自衛隊に依存しない訓練された組織であり、非常勤の特別職地方公務員でもある消防団に近いかもしれない。それに加えて、米国の連邦緊急事態管理庁(FEMA・フィーマ)のような組織を指しているのでないだろうか。
FEMAは1979年にカーター政権の下で連邦準備局、国防民間準備局、連邦災害援助局、全米消防局など、連邦政府内の複数の省庁に分散していた国内危機管理に関する組織・権限・機能を大統領直下の単一組織に集約したものだ。
そして、米国内で発生する大災害、人為的な重大事故、他国からの軍事攻撃、テロなどのあらゆる緊急事態を想定し、「準備・対応・復旧・被害軽減」の対処システムを共通化したオールハザード型の司令塔機能を持っている。
それに対して、日本は内閣府(防災担当)が国土庁に代わって防災業務を担うようになってからも、省庁ごとに防災業務の事務を分担管理(縦割行政)する体制が続き、内閣府の職員の大半は省庁や地方自治体から平均で約2年間の出向であり、専門性を持った職員が少ない非常に脆弱な体制となっている。同様に、内閣官房も省庁からの出向で成り立っている。消防庁も総務省に採用され人事異動で消防庁に勤務し、数年で総務省に戻る職員と市町村消防から出向している職員がほとんどあり、脆弱な体制となっている。
ビル・クリントン政権時代にFEMA長官を務めたジェームズ・ウィット氏は平成14(2002)年 5月29日及び同31日に兵庫県と東京都で開催された「地方公共団体の危機管理のあり方シンポジウム」において基調講演とパネルディスカッションに参加し、日本の危機管理体制の在り方についての問題点を次のように指摘している。
「日本は、多くの異なる省庁が異なる責任を持っているようである(中略)。どこが総括的な計画を持っているのか、どうやって一緒に協力していくのか、どうやって資源を調節するのか。中央のレベルから実際の地方のレベルまでどのように協力し、どうやって一定の資源から最大の効果を引き出すのか。資源は限定されており、いかに無駄を省くかなどの計画はあるのかはっきりしない」
まさに厳しい指摘である。現在もほとんど改善されていない。
日本は昨年9月1日にようやく感染症対応に特化した内閣感染症危機管理統括庁を発足させた。
この組織は、新型コロナ感染症対応の教訓を踏まえて、平時・緊急時それぞれの状況において司令塔機能が発揮されるよう、内閣の重要政策等に関する企画立案や行政各部の総合調整権を有する内閣官房の中に設置されている。
そして、平時の準備、感染症危機発生時の初動対応、行政各部との総合調整機能を一元的に所掌することになっている。本来は感染症だけでなく、あらゆる緊急事態に対応できるオールハザード型の司令塔組織(内閣危機管理統括庁へ改編)へと発展させるべきである。
一方で、災害対応は国民の協力が不可欠だ。地域の特性に応じた共助とともに、国民にある程度の義務的訓練を課すべきである。いつまでも「平和と安全」は「タダ」という意識を変える必要もある。そうすることで、日本人一人ひとりが緊急事態に対して他人事ではなく自分事として捉える意識を持つようになり、日本全体の危機管理力のレベルアップにもつながる。
緊急事態条項の明記を
「国難」級のあらゆる緊急事態を想定し、国会が開けない場合に、政府(内閣)が一時的に法律と同じ効力を持つ政令を制定できる規定を日本国憲法に設けることも必要だ。つまり、国家の骨格である憲法に「平時」から「緊急時」にスイッチの切り替えがスムーズにできる緊急事態条項を明記するべきである。
2024年3月4日・18日 週刊「世界と日本」第2264・2265号 より
災害ボランティアの進化と課題
京都大学 防災研究所教授
矢守 克也 氏

《やもり かつや》
京都大学防災研究所教授。専門は、防災心理学。現在、日本災害復興学会会長、地区防災計画学会会長、日本災害情報学会副会長、自然災害学会副会長。防災功労者防災担当大臣表彰、兵庫県社会賞などを受賞。主な著書に、『防災心理学入門』、『防災人間科学』、『現場でつくる減災学』、『巨大災害のリスク・コミュニケーション』など。
日本社会における災害ボランティアについて考えるとき、その現代的なスタート点が、来年(2025年)1月で発生から30年となる阪神・淡路大震災(1995年)にあることは間違いない。「ボランティア元年」という言葉も誕生し、全国からのべ180万人もの人びとが被災地で活動したとされている。
ただし、この点については、但し書きを添えておく必要がある。まず、阪神・淡路大震災以前、災害ボランティアがまったく存在しなかったわけではない。例えば、昨年(2023年)、発生から100年を迎えた関東大震災(1923年)でも、被災地の大学生などが「学生救護団」を立ち上げたとの記録が残っている。「学生救護団」は、救援物資の配布、犠牲者や負傷者の名簿作成などに従事したという。
ちなみに、被災後、救護団の活動の継続か学業への復帰かをめぐって葛藤があったと史料に記されている。同じような話は、東日本大震災、さらに、今年元日に発生した能登半島地震の被災地からも聞こえてくる。災害ボランティアという呼称の有無を別にすれば、同種の活動の歴史は相当昔にまでさかのぼることができる。
次に、「ボランティア元年」の意味は、災害ボランティアが日本社会における防災・減災や復旧・復興の全体に及ぼしたインパクトの大きさに求める必要がある。大きなインパクトとは、一言で言えば、「だれが担うのか?」に関する常識の一大転換である。「瓦礫の下からの救助活動、それは警察・消防、自衛隊がすることだ」、「避難所の運営は行政職員の仕事でしょう」。ボランティアらの活躍は、このような先入観を大きく変えた。災害とは「社会全体で向き合うものだ」という新しい常識の誕生である。
このことを象徴する言葉もまた、阪神・淡路大震災とともに生まれた。「自助・共助・公助」である。念のために辞書的な意味合いを注記しておく。「自助」とは個人や家庭における災害への備え、「共助」とは地域コミュニティにおける助け合いをベースとした防災活動、「公助」は国や自治体の防災への取り組み、である。この点について、「公助には限界があるから、防災では自助・共助が大切だ」、「過疎高齢化や近隣関係の希薄化によって共助が弱体化しているため、公助の充実が必要だ」など、「自助・共助・公助」間の責任の「押し付け合い」とも受け取れる論調が近年目立ってきた。「ボランティア元年」の原点が、「だれが担うのか?」に対して、「あなた(たち)でしょう」ではなく、だれもが「わたし(たち)です」と応じる社会への転換にあったことを思い出す必要がある。
さて、災害ボランティアの今は、複数の対立軸をもとに整理することができる。災害ボランティアはどうあるべきかをめぐって、いくつか異なる考え方が存在するということだ。これらの軸は、一面では災害ボランティアが進化を遂げてきたことの証左だし、他面では解消すべき課題も同時に存在するということでもある。
第1は、災害ボランティアは、国や自治体による公的な活動の補完物なのか独自性を有するのか、という軸である。ボランティアなのだから当然後者だろうという向きもあるかもしれない。しかし、現実には、ボランティアセンターと呼ばれる窓口が、行政と密接な関係をもつ社会福祉協議会によって開設され、多くのボランティアがこの窓口を通して活動している。また、「補完物」というと聞こえは悪いが、これを行政との「協働・共同・連携」と言い換えるとニュアンスが変わるし、「独自性」も、「独断・気儘(きまま)・閉鎖」と置き換えると、まったく問題がないわけではないように思えてくる。
なお、この点については、「(今は)ボランティアは来ないでください」を、ボランティアセンターや行政が口にすることの是非をめぐる論争がある。例えば、熊本県の球磨川流域での豪雨災害(2020年)ではコロナ禍が災いして、また、能登半島地震(2024年)では劣悪な道路事情などが影響して、このメッセージが発信された。「来ないで」の背景や事情も理解できないことはないが、助けを必要としている人たちがそこに存在するのに、国や自治体が統制的にアクセルやブレーキを踏むことに対する反発も根強く存在する。
第2の軸は、災害ボランティアの活動スタイルに関するもので、単純化すれば、「組織的・体系的」対「流動的・即興的」の対立となる。前者は、地元行政や他の支援団体の活動との連携のもと、活動の計画性や系統性を重視するスタイルで、より多くの被災者に共通するニーズを均等に満たすことを目指す場合が多い。他方、後者は、個人ボランティアや小規模な団体が、活動の柔軟性や機動性を重視するスタイルで、少数の被災者の個別的なニーズに細かく対応することを目指す場合が多い。
これ以外の軸については、要点だけを列挙しておこう。第3の軸は、「専門ボランティア」対「一般ボランティア」であり、前者は、例えば、重機の操縦ができる人、看護や保健衛生に関する専門的な仕事に従事できる人などを指し、近年、「プロボノ」という言葉も普及してきた。第4の軸は、「短期集中」対「長期定着」であり、被災後短い時間に集中して支援活動を行う前者と、生活再建や地域再生の過程に長い期間「伴走」する後者との違いである。
いずれにしても、ここでは対立軸と銘打ったが、「どちらが望ましいか」、「どちらを選ぶか」という観点から提示したものではない。どの対立軸においても、対照されている2つの方向性の双方に長所と短所がある。時々の状況、そして、何よりも、被災者(被災地)は何を求めているのかという観点に立って、もっとも望ましい組み合わせ(ベストミックス)を探ることが、災害ボランティアには求められていると言える。
2024年2月19日号 週刊「世界と日本」第2262号 より
「政治とカネ」の問題から脱却するためには
日本大学 名誉教授
岩井 奉信 氏

《いわい ともあき》
1950年東京都生まれ、慶應義塾大学大学院博士課程修了。常磐大学教授を経て2000年より日本大学法学部教授、2021年より現職。参議院の将来像を考える有識者会議委員、政治資金適正化委員会委員などを歴任。
自民党の派閥パーティーをめぐる裏金問題は、派閥の解体という自民党政治の根幹を揺るがす事態に発展した。そして、この事件は日本政治における「政治とカネ」との根深い関係を改めて浮き彫りにした。
3人の政治家が立件されたとはいえ、深く関わったとされる有力な政治家が不起訴になり、国民の政治に対する怒りと不信は極限に達している。30年以上も「政治とカネ」の問題に関わってきた筆者としては慚愧(ざんき)に堪えない。
この事件は、政治資金収支報告書への不記載という明らかな違法行為を組織的に多くの政治家が長年にわたり行ってきたという意味で、過去に類例を見ない悪質なものである。派閥や政治家の順法意識の欠如の背景には自民党や安倍派などの「一強多弱」にもとづく「奢り」のあったことは否定できまい。
今回、改めて明らかになったことは、日本の政治資金制度の脆弱性である。この事件を例に取ると、政治献金に比べ規制が少なく誰もが券を買えた政治資金パーティーは政治献金の「抜け道」として活用されてきた。20万円を超えてパーティー券を買った者は、その氏名を明らかにすることが求められているが、分散して購入すれば氏名を明らかにする必要がない。そもそも報告をチェックする仕組が無いのだから、パーティーの売上げ自体も信用できるかどうか疑わしく、その実態は不透明だ。これは政治献金も例外ではない。政治資金収支報告書についても内容をチェックする仕組は弱く、報告されている金額が本当かどうかを検証する手段はない。
実は政治資金収支報告は政党や政治家などの「良心」に委ねられており、日本の政治資金制度は「性善説」の上に成り立っているのである。その制度を作っているのが政治家であることを考えると、実に「甘い」制度だと言わざるを得ない。今回の事件では、派閥や政治家が、それすらも守れなかったのだから開いた口がふさがらない。
振り返ってみれば、1988年に発覚したリクルート事件を契機に「政治とカネ」の問題が浮上し、政治改革が実現した。「ザル法」呼ばれた政治資金規正法も抜本的に改正され「政治とカネ」の問題は正常化したはずであった。
しかし、実際には、政治資金制度にはさまざまな欠陥や「抜け道」があることをこの事件は浮かび上がらせた。今回、政治改革の出発点になった1989年の「自民党政治改革大綱」が注目されているが、それは「大綱」に書かれた改革の「原点」や「理念」がないがしろにされてきたことを示しているのである。
では、政治改革の「原点」や「理念」とは何か。言うまでもなく、それはリクルート事件に端を発した「政治とカネ」の問題である。選挙制度改革も同士討ちが不可避で政治家本位の中選挙区制から政策論争を促進する政党本位のものにすることで「カネのかからない政治」を実現しようとするものであった。そして政治資金制度も政党以外への企業・団体献金の禁止や公開基準の引き下げによる透明性確保などの改革が行われた。
その一方で政治家に都合の良い制度や「抜け道」も生み出された。その結果、現在の政治資金制度は少なからず問題のあるものになってしまっている。
今回の事件を受け、現行の政治資金制度の改革に向けた議論が盛んになっている。すでにやるべきメニューはかなり明確になってきたと言ってよい。ただし、対処療法的改革は政治資金制度を複雑化するだけでなく、新たな問題も生みかねない。求められるのは抜本的で体系的な政治資金制度の改革である。その意味では「自民党政治改革大綱」だけでなく「第八次選挙制度審議会答申」など、さまざまな提言を参考にその「原点」や「理念」にもとづく「原則」を明確にした上で、改革の議論を行う必要がある。
ここから析出(せきしゅつ)されるのは、「政党本位」、「透明性の確保」、「監視体制の強化」、「公私の峻別」、「制裁の強化」の五つの原則であろう。これらの「原則」にもとづけば、政治資金制度改革で何をなすべきかが明らかになる。たとえば「政党本位」という点では、政治家単位となっている政党支部への企業・団体献金の受入は禁ずるべきだし、「透明性の確保」という観点からは「現金授受の禁止」やパーティー券の公開基準の引き下げが、「監視体制の強化」という点では「政治資金収支報告書」のデジタル化で広く政治資金の収支をチェックしやすくすることや政治資金を「管理」し「監督」する独立した機関の創設が導き出される。そして「制裁の強化」では、いわゆる「連座制」の導入が求められることになる。さらに問題となった「政策活動費」の廃止や透明化は、政治資金と政治家個人とを分離するという意味で「公私の峻別」と「透明性の確保」に位置づけられる。
言うまでもなく「政治とカネ」の問題は政治不信の最大の要因である。その一方で、民主主義の政治には一定のコストがかかることも否定しない。その意味では、政治資金改革をめぐっては、冷静で合理的な議論が行われるべきである。ヒステリックな感情論や過度のポピュリズムは理論的な制度改革を妨げることにもなりかねない。そう考えれば、政治資金制度改革に臨む政党や政治家は、一方で有権者の「声」に耳を傾けつつも「原則」を見据えて事に向かうべきだ。これを「政局の具」とするならば、まっとうな政治資金制度改革は破綻しかねない。
「政治とカネ」に対する国民の不信は、政治そのものに対する不信と同義である。「政治とカネ」に関する不信を払拭することは、政治への信頼回復の第一歩にほかならない。厳しい目を向けられているのは自民党ばかりではなく野党にも向けられている。そして改革の成否は国民の関心にも負っている。「政治とカネ」の問題から脱却するために、厳しい目が求められている。
もっとも「政治とカネ」の問題は政治資金制度の改革で済むわけではない。カネがかかると言われる政治構造を変える必要もある。それは「地盤培養」と呼ばれる地方政治との関係であり、後援会を軸とする選挙活動である。これらは政治の世界に深く根ざしたものである。この構図を変えなければ「政治とカネ」の問題はいつでも起きるだろう。「政治とカネ」の問題から脱却することは、日本の「政治文化」を変えることでもある。
2024年2月5日号 週刊「世界と日本」第2262号 より
令和6年政局展望
「岸田政権は難局を乗り切れるか」
政治評論家
伊藤 達美 氏

《いとう たつみ》
1952年生まれ。政治評論家 (政治評論 メディア批評)。講談社などの取材記者を経て、独立。政界取材30余年。中曾根内閣時代、総理官邸が靖国神社に対し、“A級戦犯”とされた英霊の合祀を取り下げるよう圧力をかけた問題を描いた「東條家の言い分」は靖国神社公式参拝論争に一石を投じた。著作多数、夕刊フジ「ニュース裏表」(木曜日発売)、自由民主「メディア短評」の執筆メンバー。ラジオ日本報道部客員解説委員。
令和6年の政局はどう動くか
昨年は岸田首相が解散に踏み切るかどうかが注目された一年だった。
筆者は岸田首相が「反撃能力保有を含む防衛力の抜本的強化」「異次元の少子化対策」「原子力の活用やマイナンバーカードの普及」などの政策を本格的に進めるのであれば、解散は不可避だろうと予想していた。信を得ずして、こうした賛否の分かれる課題を成し遂げることはできないと考えたからだ。
しかし、結果的に岸田首相は解散しなかった。この判断は岸田政権にとって致命的だった。これにより岸田首相は「解散できない首相」の烙印が押されることとなった。「解散できない首相」とは、すなわち「信を失った首相」と同義だ。支持率が下がるのは当然の結果と言える。
さらに派閥の政治資金パーティーをめぐる事件がこれに追い打ちをかけた。派閥主催の政治資金パーティーで、所属議員がパーティー券をノルマ以上販売した際、その分の収入を政治資金収支報告書に記載せず、「裏金化」したとされる。
事件報道を受け、国民の政治不信は一気に高まった。岸田政権だけでなく、自民党の支持率も急落した。その勢いは、野党に転落した麻生太郎内閣時代を凌駕するものがある。
はたして、岸田政権はこの難局を乗り切ることができるのか。
一部には岸田政権の「3月退陣」を予想する説も出ている。しかし、筆者はその可能性は低いと考えている。
まず、来年度予算審議を控え、「岸田おろし」に動きにくい状況がある。また、今、急いで岸田首相を引きずりおろしても、この局面を収拾できる見通しはない。
逆に、会期途中で政権を投げ出されて困るのは、むしろ自民党の方ではないか。なぜなら、首相辞任に伴って行われる首班指名選挙に、総裁選を経ずに臨まなくてはならないからだ。
話し合いでうまく後継総裁を一本化できれば良いが、話し合いがまとまらなければ複数の自民党議員が首班を争う「40日抗争」の二の舞となりかねない。当時は自民党に求心力があり分裂せずに収まったが、現在はそうはいかないだろう。場合によっては、自民党崩壊につながりかねない。そんな状況になるのは「できれば避けたい」というのが、自民党の大多数の「感覚」ではないか。
結局、首相自身が政権担当意欲を失わない限り、通常国会の会期末までは、岸田政権が続くことになるのではないか。
では、その後どうなるか
状況によって三つのケースが考えられる。
一つ目は通常国会終了後に辞意表明するケースだ。岸田政権への批判が今以上に高まれば、さすがに辞任せざるを得ない。この場合、9月に予定されている総裁選を前倒しし、早急に後継総裁を選ぶことになるだろう。新総裁が決まり次第、臨時国会を召集して、岸田内閣総辞職、新内閣発足という運びとなる。
二つ目は、支持率が多少回復し、政局が小康状態であれば、辞意表明せず、9月の総裁選まで状況を見極める選択肢だ。この間に状況が好転しなければ「総裁選不出馬」に追い込まれるが、変わることもあるかもしれない。その可能性に賭けようというわけだ。
三つ目は通常国会で岸田首相が解散に打って出るケースだ。このシナリオには二つのパターンが考えられる。
その一つは、支持率が、総選挙ができる水準まで回復するパターンだ。現時点では考えにくいが、「一寸先は闇」とも言われる政界だ。可能性として「ゼロ」ではない。
もう一つは、内閣不信任案可決、あるいはそれと同等の状況が出現したときだ。
戦後、不信任案が可決したのは4例あるが、いずれも総辞職ではなく、解散を選択している。また、小泉純一郎内閣の郵政解散や民主党の野田佳彦内閣の「近いうち解散」のように、窮地のなかで解散した例もある。そうした事態が出現すれば、岸田首相も先例にならって解散に踏み切る可能性はありうる。
いずれにせよ、難局を乗り切るためには、自民党が「岸田おろし」を本格化させる前が勝負だろう。
岸田首相は自らを本部長とする政治刷新本部を設置、政治資金の透明性の拡大や、派閥のあり方に関するルール作りなどについての議論を開始した。そこで、なんとしても国民の理解の得られる改革案をまとめ、支持率向上につなげたいところではないか。
一方、現在の国民の関心は「政治とカネ」の問題に集中しているが、内政の最大課題は、30年余にわたって日本経済を苦しめてきたデフレからの脱却を果たせるかどうかだろう。
岸田政権発足以来、経済が回復基調に転じているのは間違いない。コロナ禍収束の追い風もあるが、岸田政権がコストカット型経済から「適正な価格転嫁と賃金上昇」へ大きく舵を切ったことが大きな要因といえる。問題は、ロシアのウクライナ侵略の影響などによる予想以上の物価上昇で、名目賃金の上昇効果を減殺していることだ。
デフレ脱却のカギを握るのが今年の春闘にあることは多くの専門家が指摘するところだ。岸田首相は昨年、所得税減税という「禁じ手」にまで踏み込んで、環境整備に努めてきた。はたして、これが功を奏するかどうか。もし、デフレ脱却に成功すれば、支持率回復のプラス要因となるだろう。
今年は辰年である
正月早々、石川県能登半島で震度7の大地震が発生して甚大な被害をもたらした。また翌日には東京・羽田空港の滑走路上で日本航空と海上保安庁の航空機が衝突する事故が発生した。
わが国周辺の安全保障環境も緊迫の度を深めている。尖閣列島周辺には連日のように中国公船が出没し、北朝鮮のミサイル発射頻度も増えている。また、年明け早々、北朝鮮が韓国との国境線に砲弾を撃ち込むなど不穏な動きを見せている。何が起こるか分からない。
過去を振り返ると、戊辰戦争(1868年)、日露戦争(1904年)が辰年に起きている。また、ロッキード事件(1976年2月)やリクルート事件(1988年6月)といった汚職事件も辰年に発生した。また、戦後5回の辰年のうち、3回の総選挙が行われている。どうやら、政治が激しく動く年回りなのかもしれない。
(1月15日記)
2024年1月15日号 週刊「世界と日本」第2261号 より
国内外において、積極的であれ
日本大学 危機管理学部教授
先﨑 彰容 氏

《せんざき あきなか》
1975年東京都生まれ。専門は近代日本思想史・日本倫理思想史。東京大学文学部倫理学科卒業。東北大学大学院博士課程修了後、フランス社会科学高等研究院に留学。著書に『未完の西郷隆盛』、『維新と敗戦』、『バッシング論』、『国家の尊厳』など。
令和六年のわが国はどこへ向かうべきか。あるいは、どこへ向かうことを強いられるのか。まずは昨年を振り返ることから始めてみたい。
故ジャニー喜多川氏による性加害問題は、若者たちへの影響力も大きな事件であった。華麗な演技と歌唱力を売りにした男性陣たちが性加害の被害を恒常的に受け、それを報道・告発する自助能力を、マスコミ全体が持てなかった。この「性」をめぐる問題は、法改正の場面で政治にも飛び火した。LGBTなどの、いわゆる性的少数者の権利擁護をめぐり、「LGBT理解増進法」が拙速に可決成立したからである。ほぼ同時期、世界経済フォーラムが六月に発表したジェンダー・ギャップ指数で、相変わらず男女不平等の状態を非難されたことも想起しておくべきだろう。なぜなら、性的少数者や女性が蔑(ないがし)ろにされているという主張は、フランシス・フクヤマが著書『IDENTITY』で強調したように、自己承認欲求を争点とする「尊厳の政治」を生み出したからである。
もう一つ、昨年、我々を震撼させたのが、旧統一教会の解散命令請求であろう。元総理大臣の暗殺を引き起こしたこの事件で、クローズアップされたのが、いわゆる宗教二世の存在である。生まれた瞬間から信仰を強要され、精神的金銭的苦痛から解放される可能性が絶望的な中で事件は起きた。事件が起きるまで、彼らの存在はジャニーズ問題同様、黙認されつづけてきたのであり、不当なお布施の強要などを引き起こした宗教団体が、政治の指示により解散される可能性がでてきたのだ。
こうした一見、バラバラに起きている事件を、どう理解すればよいのか。あえて共通点を探り出し、そこに「令和日本が直面する課題」をあぶりだすとどうなるか。恐らく次の二点に注目すべきだと筆者は考えている。
第一に、「性」が全面にせり出してきたことに注目する。「性」は、その多様性も含めて人間の最も根源的な、最深部の存在意味を与えているものである。本来は秘されているべき「性」が、白日の下で論じられるようになったことは、要するに、現代社会がプリミティブに、原始的になっているということである。性、民族、肌の色、宗教など、原始的・根源的な問題が、私たちの眼の前に現れたということだ。
第二に、国内でみた場合、「戦後システム」の賞味期限が決定的に切れたとみるべきである。ジャニー喜多川氏が日米を架橋し、戦後のエンターテイメントの基調を創ってきたことは間違いない。と同時に、日本型男女不平等の象徴である家族モデル自体、戦後に生み出されたものである。さらに宗教に注目すると、戦前への反省から、戦後のわが国は「政教分離」を徹底し、宗教の分野に政治権力が介入することには極めて抑制的であった。これは、「個人の内面にかかわる思想信条については、政治権力は一指も触れない」ことが正しいという前提である。しかし今回の事件が突きつけたのは、私たちの心から、たとえ政治権力を排除したとしても、その心は決して自由でも開放的でもない、という事実だった。つまり、エンターテイメント・日本型家族像・政教分離の無条件肯定という「戦後システム」全体が崩壊した。旧来のシステムが崩壊した光景には、極めて原始的な性や肌の色、宗教をめぐる差別意識や暴力が、頭をもたげてきているのではないか。
以上の問題意識をもって世界へ眼を向けてみよう。三年目に突入するウクライナ戦争に加え、中東情勢が激変したことは、記憶に新しい。だが、私が注目したいのは、こうした目立った戦闘行為ではない。背後から忍び寄り大きな渦を描くように広がる、もう一つの潮流である。それは米国と欧州で混乱を引き起こしている移民問題のことだ。テキサス州など中米国境に接し、多数の不法移民が流入する州から、移民に寛容とされる大都市―聖域都市と呼ばれる―に、バスで移送する措置が取られているからだ。ニューヨークだけではない、シカゴやロサンゼルスの街角には、今、移民があふれ急速に治安が悪化している。現在、中南米は急速に中国との関係を深めている。米国はウクライナや中東安定化に必死だが、その傍らで中南米問題を抱えているのだ。
目を欧州に向けてみよう。そこにはさらに深刻な移民問題に苦悩するヨーロッパの姿がある。わずか人口6千人の小島に、一週間で1万人を超える移民が殺到し、イタリアは対応に追われている。その背景には、ギニアやコートジボアールなどサハラ砂漠以南から、砂漠と地中海を越えて決死の移動をいとわない移民も含まれている。すでにウクライナ難民を抱える欧州では、新たなアフリカ発の移民に対し対応の足並みは乱れている。つまり現在、G7でイメージされる欧米先進国、自由と民主主義の価値観を日本と共有する国々は、戦争と移民問題に忙殺されているのだ。
以上から分かるのは、日本国内では「戦後システム」の賞味期限が切れ、国際社会は混乱の度合いを深め、欧米先進国が苦悩する姿である。
そこに今年、重大な選挙が各国で目白押しであることは周知のとおりだ。だとすれば、日本がとるべき進路は明確ではないか。
具体的には、原始的な差別や暴力を抑制するために、政治が先頭を切ることが必要である。性的少数者や「性」差別の糾弾が、時に行き過ぎた政治運動になることは、先にふれたフクヤマが昨年刊行した『リベラリズムへの不満』を一読し、冷静に国家像を定める必要があるだろう。また一方で、国際社会に対しては、岸田内閣が内向きになってはならない。自民党の不祥事を理由に、南米訪問をキャンセルしたことは決定的な失策なのであって、今、わが国がすべきは、あえて南米を訪問し、地域の混乱に金銭的支援を含めたプレゼンスを高め、移民問題で苦しむ欧米諸国にたいし、日本の存在意義を高めることだ。
今年、日本のなすべきこと、それは「国家像」を具体的な課題に落とし込み、実現する行動力である。
2024年1月15日号 週刊「世界と日本」第2261号 より
2024年景気見通しと再生への展望
大阪経済大学 特別招聘教授 経済評論家
岡田 晃 氏

《おかだ あきら》
1947年大阪市生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業後、日本経済新聞社に入社。記者、編集委員を経てテレビ東京に異動。WBSプロデューサーを経て、ニューヨーク支局長、テレビ東京アメリカ初代社長、テレビ東京理事・解説委員長。06年より経済評論家として独立し、大阪経済大学客員教授に就任、22年より同特別招聘教授。主な近著に『徳川幕布の経済政策—その光と影』。
新しい年、2024年を迎えた。国際情勢の緊迫や海外経済の減速など、日本経済を取り巻く環境は相変わらず厳しい。それでも2024年は、民間企業の収益力回復やインバウンドの急回復などを支えに、緩やかながら着実に景気回復が続くと見ている。ただ政治の不安定化などリスクも多い。2024年は日本経済の本格復活に向けて重要な年となるだろう。
2023年は「過去最高、バブル期以来」など続出
まず2023年を振り返ろう。ウクライナ危機に加え、イスラエル・パレスチナの軍事衝突で国際情勢は一気に緊迫。中国では習近平体制の強権化が目立つ一方で、景気減速が顕著となり、特に不動産不況は深刻だ。
このため世界経済は減速傾向となっている。IMF(国際通貨基金)の「世界経済見通し」(2023年10月改定)によれば、2023年(暦年)の実質GDP(国内総生産)成長率は世界全体で3・0%となり、2022年実績の3・5%から鈍化すると見込まれている。IMFの数字としてはかなりの鈍化だ。
だが2023年の日本経済はこのような厳しい環境下でも景気回復を持続した。実は2023年は、経済指標で過去最高、あるいはバブル期以来などの記録が続出した年でもあった。
2023年のGDPの実額は、発表済みの7—9月期までの各四半期ともコロナ前のピークだった2019年の各四半期を実質でも名目でも上回り、過去最高額となった。国の税収も過去最高額だ、消費者物価上昇率は41〜42年ぶり、賃上げ率は30年ぶりの高い伸び。12月の日銀短観では非製造業の業況判断指数が32年ぶりの高水準となった。
日経平均株価は5月に33年ぶりとなる3万円台をつけ、7月には3万3700円台とバブル崩壊後の最高値を更新した。その後も高値圏で推移しており、年初からの上昇幅は約8000円、上昇率は約30%に達している(2023年12月27日時点)。
日頃のメディアの報道では日本経済の「低迷」「弱さ」ばかりが強調されている。確かに回復はまだではないが、それでも実際には長年の低迷から脱して強さを取り戻しつつあることは間違いない。
こうした経済回復の要因は、①コロナの「5類」移行による経済活動の正常化②世界的インフレの一応のピークアウト③企業業績の好調持続④インバウンドの急速な回復—などが挙げられる。
2024年も景気回復持続へ
これら4つの要因は2024年も継続し、緩やかながら景気回復が持続するだろう。特に筆者が注目するのは③の企業業績と④のインバウンドである。
企業業績については、2023年3月期の全上場企業の最終利益は3期連続で増益かつ2期連続で最高益となった。コロナ禍の3年間でも増益を続けていたわけで、このことは日本企業が経営の構造改革と競争力強化の努力を続けてきた成果が実を結び始めたことを示している。2024年3月期も、現時点では13%程度の増益見通しとなっている(日本経済新聞)。
またインバウンドは2023年10月の訪日客数が単月でついにコロナ前を上回った。訪日外国人の旅行消費額はすでに2023年7—9月で1兆3900億円、2019年同期比で17・7%増に達している(観光庁推計)。中国からの訪日客がまだほとんど戻ってきていないにもかかわらず、これほどまでに増加しているのは、世界中に日本人気が広がっていることを示している。
2024年もさらなる増加が見込まれる。と同時に、このインバウンドブームが幅広い分野での日本産製品の輸出増加や地方の活性化といった新たな可能性を広げることにもなり得る。
今見てきた企業業績の好調持続とインバウンド回復は、中長期的にも日本経済の完全復活に向けてけん引力となりうるものだ。これに加えて、物価上昇に対応する賃上げと設備投資の増加が実現すれば、2024年の景気回復持続はより確実なものとなるだろう。
こうした見通しを背景に、2024年の年末までに日経平均株価は1989年12月の史上最高値(3万8915円)を更新してもおかしくない。年間の上昇率が20%になれば、4万円の大台を軽く超える計算になるのである。
「辰年は政変」のジンクス、政策停滞に警戒必要
だが一方で、懸念材料が山積なのも事実だ。従来からのウクライナ情勢や中東情勢、中国の政治動向と経済失速懸念などに加えて、2024年は日本と米国の金融政策に絡んだ為替リスクや米大統領選を巡るリスクにも注意が必要だ。
さらに国内の政治リスクが浮上している。実は「辰年は政変」というジンクスがある。
▷1964年 池田首相が癌のため退陣を表明し佐藤内閣が発足
▷1976年 総選挙で自民党が過半数割れで三木首相退陣、福田内閣発足
▷1988年 リクルート事件。翌年に竹下首相退陣
▷2000年 小渕首相斃れ、森内閣発足
▷2012年 総選挙で民主党大敗し野田首相退陣、第二次安倍内閣発足
そして2024年。すでに2023年末から政局は大きく動き出した。「政変」による経済停滞のリスクには特に警戒が必要だ。日本経済は景気回復と言ってもまだ不十分であり、少子高齢化やデジタル化など構造的な課題を抱え、いまだにデフレ・マインドが根強い。それを払拭して本格的な経済復活を実現するには改革が不可欠だ。政治のリーダーシップが問われる一年になることは間違いない。
2024年1月1日号 週刊「世界と日本」第2260号 より
自由と独立は勝ち取るものだ
麗澤大学客員教授
江崎 道朗 氏

《えざき みちお》
1962年、東京都生まれ。九州大学卒業後、国会議員政策スタッフなどを経て2016年夏から評論活動を開始。主な研究テーマは近現代史、外交・安全保障、インテリジェンスなど。産経新聞「正論」執筆メンバー。2023年、フジサンケイグループ第39回正論大賞を受賞。最新刊に『なぜこれを知らないと日本の未来が見抜けないのか』(KADOKAWA)。
我が国はいま、安全保障政策を大きく転換しつつある。
驚くべきことに、戦後日本の安全保障政策の基本は長らく「国連中心主義」と「対米依存」だった。
1957(昭和32)年に閣議で決定された「国防の基本方針」は次の4項目だ。
①国連の活動を支持し、国際間の協調をはかり、世界平和の実現を期する。
②民生を安定し、愛国心を高揚し、国家の安全を保障するに必要な基盤を確立する。
③国力国情に応じ自衛のため必要な限度において、効率的な防衛力を漸進的に整備する。
④外部からの侵略に対しては、将来国連が有効にこれを阻止する機能を果たし得るに至るまでは、米国との安全保障体制を基調としてこれに対処する。
要はいざとなれば国連と米国に守ってもらおう、と考えてきたわけだ。この国連中心主義と対米依存の防衛方針を大きく変えたのが、安倍晋三元首相だった。
そもそも日本には、自国の自由と平和をいかに守るのか、独自の国家戦略がなかった。中長期的な国家戦略がないから、その場しのぎを繰り返し、いざとなれば米国に従う「半独立国家状態」であったわけだ。
しかし北朝鮮のミサイル・核開発、中国の軍事的経済的台頭、そして米国の相対的な力の低下という情勢のなかで対米依存だけで我が国を守っていくことができない。
そこで第二次安倍政権は2013年、日本独自の国家安全保障戦略を初めて策定した。
この国家戦略の注目点は3つだ。第1に、国連に頼ることをやめたことだ。第2に「我が国の能力・役割の強化・拡大」を掲げたことだ。「自分の国は自分で守る」覚悟があってこそ、米国も助けに来てくれるという方針を明確にしたのだ。第3に、米国以外の国とも安全保障協力を強化する方針を打ち出したことだ。
この国家戦略を遂行するため特定秘密保護法や平和安保法制を成立させ、豪、英、仏、加、印などと物品役務相互提供協定を締結し、米国以外の国との軍事・情報両面での連携を拡大してきた。英・豪とはいまや準同盟国のような関係で、日本周辺では頻繁にこれら同志国の軍隊との合同演習を行うようになってきている。
並行して対米追従から対米説得へと、外交姿勢も転換させつつある。その象徴が「自由で開かれたインド太平洋構想(FOIP)」だ。2017年11月、安倍元首相からFOIPを聞いたD・トランプ大統領は翌18年2月、FOIPを米国の対外戦略に採用した。戦後、日本の対外戦略を米国が採用したのはこれが初めてのことだ。
2022年12月、岸田文雄政権は国家安全保障戦略を改定、5年間で43兆円を投じて防衛力を抜本強化する方針を決定した。それは、我が国の自由と平和を脅かす脅威がますます深刻になっているからだ。
脅威の第一は中国だ。《十分な透明性を欠いたまま、軍事力を広範かつ急速に増強》し、《東シナ海、南シナ海等における、力による一方的な現状変更の試みを強化》するだけでなく、《台湾について武力行使の可能性を否定せず、また、台湾周辺における軍事活動の活発化》させている。
第二が北朝鮮だ。《拉致問題は、我が国の主権と国民の生命・安全にかかわる重大な問題であり、国の責任において解決すべき喫緊の課題》であり、《ミサイル関連技術及び運用能力の急速な進展。核戦力を最大限のスピードで強化する方針》を掲げている点も深刻だ。
第三がロシアだ。《ウクライナ侵略、北方領土での軍備増強及び活動活発化、中国との戦略的な連携の強化》は《安全保障上の強い懸念》となっている。
よって近い将来、《インド太平洋地域において、国際秩序の根幹を揺るがしかねない深刻な事態が発生する可能性》が高く、しかも《こうした動きの最前線に位置》する我が国としては、自由と平和を守るため、中長期的な展望をもって周到に準備を整えておく必要がある。
そこで岸田政権は、2段構えの国家戦略を打ち出した。まずは《危機を未然に防ぎ、平和で安定した国際環境を能動的に創出し、自由で開かれた国際秩序を強化するための外交》を繰り広げるというものだ。
そのために①日米同盟の強化、②自由で開かれた国際秩序の維持・発展と同盟国・同志国等との連携の強化、③我が国周辺国・地域との外交、領土問題を含む諸懸案の解決に向けた取組の強化などを推進する。
要は北朝鮮、中国、ロシアといった「脅威」から《自由で開かれた国際秩序》を守ろうと思う同志国を増やそうというわけだ。
というのも、中国を「脅威」だと思っている国は必ずしも多くないのだ。米国では、D・トランプ共和党政権以来、中国に対する警戒心が超党派で強まっている。
だが欧州は違う。例えば、「欧州外交問題評議会」は昨年6月7日、台湾と中国をめぐる衝撃的なリポートを公表した。何と欧州連合(EU)加盟11カ国の18歳以上の成人約1万7千人を対象の世論調査の結果、「台湾をめぐって米中戦争が発生した場合、自国が中立を守るべきだ」と回答したのが全体回答者の62%に上ったのだ。要は「台湾有事に際して米国を支援すべきだ」と答えたのは3割ぐらいで、6割は中立を保つ、つまり米国や日本を「政治的に」支援するつもりがないと回答したのだ。
だからこそ日本としては、地球儀を俯瞰する外交で欧米諸国やアジア諸国を懸命に味方につけようとしているわけだが、残念ながら外交だけで紛争を未然に阻止できるとき限らない。
そこで軍事、つまり防衛力の抜本的強化に踏み切ったというわけだ。それは①我が国自身の防衛体制の強化、②日米同盟の抑止力と対処力、③同志国等との連携、の三つの柱で構成されている。
戦後長らく対米依存の安全保障政策を掲げてきた日本がついに「自国の防衛体制の強化」を第一に掲げたのだ。
国連頼み、米国頼みから「自分の国は自分で守る国」へと、我が国の安全保障政策は大きく変わった。必然的に国民の側の意識も大きく変わっていかなければならない。
自由と独立は与えられるものではない。勝ち取るものなのだ。
2024年1月1日号 週刊「世界と日本」第2260号 より
泥船漂流の岸田政権
「国民と向き合う政治家」を目指せ
評論家
ノンフィクション作家
塩田 潮 氏

《しおた うしお》
1946年高知県生まれ。慶大法卒。雑誌編集者、月刊『文藝春秋』記者などを経て独立。『霞が関が震えた日』で講談社ノンフィクション賞受賞。『大いなる影法師』、『昭和の教祖 安岡正篤』、『日本国憲法をつくった男 宰相幣原喜重郎』、『密談の戦後史』、『内閣総理大臣の沖縄問題』、『危機の権力』、『解剖 日本維新の会』、『大阪政治攻防50年』。近著に『安全保障の戦後政治史』など著書多数。
岸田文雄首相が政権存亡の危機に直面している。風雲急を告げる情勢である。
内閣支持率は、12月調査で朝日新聞23%、共同通信22・3%、時事通信17・1%と2012年12月の自民党政権復活後の最低率を更新中だ。記録的不人気に加え、自民党の派閥をめぐる「政治とカネ」の問題と、首相自身の旧統一教会系団体のトップとの面会の報道が重なり、政権は末期症状に陥った。
岸田首相は23年11月18日、アジア太平洋経済協力(APEC)首脳会議の後、報道陣に支持率低迷について聞かれ、「謙虚に受け止めたい」と型どおりの答えで受け流した。この時点では、まだ余裕があった。
帰国後、自民党各派のパーティー収入の政治資金収支報告書への不記載の問題が露見する。東京地検特捜部も「裏金」疑惑の解明に動き始めた。
だが、首相自身は表向き強気の構えを崩さず、11月28日の共同通信加盟社編集局長会議でのスピーチで「24年はまさに緊迫の1年」「内外の難局に不退転の決意で」と政権維持に強い意欲を示した。
その後、朝日新聞が12月4日の朝刊から、岸田首相が自民党政調会長だった19年10月に、来日したアメリカの元下院議長とともに、自民党本部で、旧統一教会系の日米の団体のトップ2人と会っていたと報じた。
首相はこの問題が浮上した22年8月以来、旧統一教会とのつながりについて「関係はない」と繰り返し述べてきた。面会報道の後も説明を変えていない。
一方の派閥の裏金事件は、岸田政権にとって直撃弾となった。
23年12月7日以降、内閣の要だった松野博一官房長官らの疑惑の表面化という展開となる。岸田首相は臨時国会閉幕後の14日、松野氏ら、安倍派の4閣僚の更迭に踏み切った。
この事態で、首相自身は、旧統一教会の問題、派閥の裏金疑惑とも、言い逃れの弁明に終始する。求心力消滅で、政権は死に体となり、早期首相交代論も飛び交い始めた。
落ち目の岸田首相がこの場面で持ちこたえられるかどうか。
続投の成否は視界不良だが、首相本人は逆に安倍派衰退と後継候補不在を理由に、「危機突破・政権維持」の決意を固め、八方ふさがりの状況の下で一発逆転の一手を模索しているかもしれない。
乾坤(けんこん)一擲(いつてき)の起死回生策はあるのか。
首相の特権を生かすなら、衆議院の解散・総選挙だが、23年の通常国会と臨時国会で2度、挑戦を企図して不発に終わった苦い過去がある。24年9月の自民党総裁任期満了の前の衆院選実施は総裁再選・政権維持の有力な手段だが、低支持率、疑惑噴出、求心力喪失という現状では、一点突破の解散作戦は実行困難だろう。
強行を目指せば、与党内で岸田降ろしが本格化する。民意も、首相の延命狙いの解散・総選挙には背を向けるに違いない。その壁を乗り越えるには、首相は国民に信を問うべき明確な論点を提示しなければならないが、それも見当たらない。
就任以来の持論である「新しい資本主義」の是非は、看板と標語だけで、具体的な取り組みで本気度が見えないと国民に見抜かれている。22年12月に閣議決定した安全保障3文書改定を軸とする安保政策の転換は「解散の大義」となりうるが、争点化を避けたい防衛費増額の財源問題が議論となる心配がある。
もう一つ、政権獲得時の21年9月の総裁選で「在任中に」と唱え、23年10月の所信表明演説でも「やる」と明言している憲法改正はどうか。首相が本気なら、次期衆院選の焦点として値打ちのある重要テーマだ。
といっても、実際には容易ではない。国会の党派別議員数を見ると、特に参議院で、改憲政党だけでは改憲案の国会発議の必要要件に届いていない。
改憲案の中身についても、改憲政党各党の足並みがそろっていないという問題がある。首相の在任中の挑戦は時間的に厳しいという見方が有力だ。
それを承知で、改憲について「やる」と首相が言い続けるのは、掛け声だけの見せ掛け論では、という疑いが消えない。
「死中に活」の解散作戦が不可能なら、今や風前の灯の政権を蘇生させるには、奇策や密計などの小細工は捨てて、政権の王道に立ち返るしか道はない。
岸田首相はもともと所属派閥の宏池会への執着が強い。橋本龍太郎元首相以後の過去25年の自民党首相は、麻生太郎氏を除く7人全員が就任後、派閥会長を兼任しなかったが、岸田首相は会長の座を手離さなかった。今回の裏金事件でやっと派閥離脱を決めたが、岸田政治の本質は「官僚依存」と「派閥重視」である。
政権運営でも政策判断でも、一般の国民は視野の外で、重きを置いているのは霞が関と永田町と映る。国民に向かって自身の達成目標や挑戦のシナリオを明示し、支持する民意の幅広い同意と共感を背に命懸けで取り組むのが民主政治の王道だが、それとは対極の手法と姿勢である。
ここまで状況が悪化すると、遅きに失した感があるが、岸田首相が危機を脱して再浮上を図る唯一の方策は、本物の民意結託型首相への変身しかない。
前述の11月28日のスピーチで自ら「30年ぶりのデフレ脱却のチャンス」「新しい日本経済のステージ」と訴えて、岸田流「新しい資本主義」への挑戦姿勢を表明した。空念仏に終わらせないための現実的な将来像、具体的な工程表と処方箋を打ち出し、覚悟とやる気を示す必要がある。
自ら「安倍さんもできなかったこと」「歴史的な転換」とアピールする安保政策、「やるやる詐欺」と疑われている改憲挑戦も、中身の議論とともに、首相自身の理念や方針を明らかにして、広範な民意の賛成や同意を獲得すべきだが、努力の跡が見られない。
総裁再選と政権維持のための「総裁選前の解散」といった目先の計算ではなく、王道の取り組みで民意と正面から向き合い、支持を得て、堂々と国民の信を問う。政権再生の方途はそれ以外にない。
2023年12月4日・18日号 週刊「世界と日本」第2258・2259号 より
必要な児童相談所と警察との間の
リアルタイムでの情報共有システムの整備
弁護士
ThinkKids子どもの虐待・性犯罪をなくす会代表理事
後藤 啓二 氏

《ごとう けいじ》
1959年神戸市生まれ。82年東大法卒、警察庁入庁。大阪府警本部生活安全部長、愛知県警警務部長などを歴任。2004年内閣参事官(安全保障・危機管理担当)。05年警察庁を退職し、弁護士登録。08年後藤コンプライアンス法律事務所(神戸市)を設立。
1 本年に入り『神戸市修くん虐待死事件』、『大阪府大東市母親による薬物投与女児入院事件』、『奈良県橿原市星華ちゃん虐待死事件』等虐待死あるいは命の危険が高かった重大な虐待事件が多発しています。
これらの事件では、いずれも児相や市町村が関与していましたが、みすみす虐待死、あるいは命の重大な危険に至らしめています。
児童相談所や市町村が関与しながら、必要な対応をせず、子どもをみすみす虐待死に至らしめる事件は、これまでも『東京都目黒区結愛ちゃん虐待死事件』、『岡山市真愛ちゃん虐待死事件』、『大阪府摂津市桜利斗ちゃん熱湯を浴びせての殺人事件』等全国で数多く発生しています。その多くは、児童相談所や市町村が、縦割りのまま、案件を抱え込み、警察に案件すら知らせず、親の言い分どおりに、自ら保有するわずかな情報に基づき、自分たちだけで虐待リスクを甘く判断し、警察と連携してより頻繁に家庭訪問し子どもの安否を確認する、一時保護するなど子どもを守るために必要な対応をしなかったことが原因です。本年に発生したこれらの事件もまさにそのような対応をしてしまった事件です。
2 私どもは、これらの事件を受け、神戸市長、大東市長、奈良県知事に要望書を提出し、記者会見しました。要望の主な内容は共通しており、次のとおりです。
『児童相談所や市町村は、虐待の兆候が認められる案件について、独断で、安易に「虐待ではない」と判断することなく、すべての虐待の疑いのある案件については、リアルタイムで最新の情報を警察と共有し、連携して子どもを守る活動を行うものとする』。
これらの事件も含め、児相や市町村が関与しながらみすみす虐待死に至ら止めるケースでは、せっかく住民や医師から通報がありながら、児相や市町村が、独断で、安易に「虐待でない」と甘いリスク判断をし、警察に連絡することなく放置し、虐待死に至らしめるというパターンで共通しています。そこで、このような対応、流れをやめ、児相や市町村が独断で安易に「虐待でない」という甘すぎるリスク判断をする仕組みを改めることができれば、虐待死をかなり減らすことができるのです。
最近では、全国の自治体でこのような理解が進み、50以上の道府県・政令指定市で、児相と警察との全件共有と連携しての活動が実現しています。
児童相談所が、独断で、安易に、「これは虐待ではない」という判断する仕組みを続ける限り、児童相談所が関与しながら虐待死させてしまう事件はいつまでもなくなりません。そのためには、児童相談所が把握したすべての案件を警察と共有し、連携して子どもを守る活動を行うことが必要不可欠なのです。
3 しかし、全件共有をしていても、情報の共有にタイムラグがあれば、連携した活動を十分に行うことができません。児童相談所と警察との間で、保有する情報の内容に差があれば、リスク評価が異なることとなり、すれ違いが起こってしまうからです。そこで、できる限り、リアルタイムで情報共有を行う仕組みが必要となっています。
この点については、現在のところ、全件共有の上連携した活動を行っている自治体でも、リアルタイムでの情報共有はそれほど行われていません。多くの自治体では、児童相談所から警察への虐待案件の通報は、通告を受けた直後に、その概要につき一覧表で連絡を受けるような方法で行われており、常時最新の状況が共有されていません。現行の情報共有の仕組みのままでは、警察も正確なリスク判断ができないことから、危険な状況にいる子どもを把握することができず、児童相談所と連携して速やかに家庭訪問するなど必要な対応をとることができない状況となっています。
児童相談所と警察の双方が、お互いに虐待案件を把握すれば直ちに必要な情報をパソコンに入力することで(その後さらに情報を把握した場合も同様)、互いに最新の状況をリアルタイムで共有できるというシステムとすれば、共有の遅れも生じませんし、警察、児童相談所とも、情報の共有に必要な業務負担を軽減し、業務の効率化を図ることができます。
このようなシステムは、既に、埼玉県・さいたま市、千葉県、三重県、青森県等で整備され、神奈川県、横浜市、兵庫県では本年補正予算で整備することとされ、急速に整備が進んでいます(各自治体により情報共有の仕組みは若干異なっています)。
そこで、全国の自治体では、全件共有はもとより、それらをリアルタイムで情報共有するシステムの整備が必要です。今回の奈良県橿原市の事件では、母親の交際男性の存在が明らかでありながら、児相も市町村も交際男性の調査もしていませんでした。情報共有システムが整備されていたら、警察がこのような状況を知れば、直ちに、虐待リスクが高いと判断し、児童相談所にその旨を連絡し、交際男性の調査は警察で行う、一緒に家庭訪問して子どもの安否を確認しよう、など児童相談所だけでは行わなかった必要な対応をとることができることになります。
4 この奈良県橿原市の虐待事件をはじめ多くの事件から明らかなことは、児童虐待対応につき、一つの機関だけでリスク判断することは子どもにとり危険極まりないということです。児童相談所、警察、市町村さらには、乳幼児担当部局、学校、医療機関、民生委員など関係する多くの機関が、縦割りを排除し、各機関の保有する情報を共有して、できる限り正確に虐待リスクを判断できるようにした上で、連携してベストの力を発揮して、子どもを守る活動を行わなければ、いつまでも子どもの命を救うことができません。
そして、虐待事件があふれかえっている中で、複数の機関が情報を共有し連携して対応するためには、関係機関での情報共有を職員の負担なくリアルタイムで行うなど業務を省力化するしかありません。書類を持参する、電話でいちいち確認するという対応では、情報共有すら十分にはできません。そのためには、上記のようなシステムを整備することが必要で、いくつかの自治体では既に整備されています。
救えたはずの子どもの命が救うことができないという事件を二度と起こさないため、私どもが要望した神戸市、奈良県をはじめ、全国の自治体で、全件共有の上リアルタイムでの情報共有システムの整備が図られるよう引き続き働きかけてまいります。
2023年11月20日号 週刊「世界と日本」第2257号 より
「終わらぬ円安、取り組むべき課題」
—円安は総合的にプラス、輸入インフレ深刻でなければ対応不要—
東洋大学
情報連携学部元教授
益田 安良 氏

《ますだ やすよし》
東洋大学、成蹊大学兼任講師、博士(経済学)。1958年生まれ。81年、京都大学経済学部卒業後、富士銀行入行。88年、富士総合研究所に転出し、ロンドン事務所長、主席研究員等歴任。2002〜23年、東洋大学経済学部、大学院経済学研究科、情報連携学部教授。16〜18年、国立国会図書館専門調査員。専門は金融、国際経済。
円安が止まらない。円・ドル為替レートは、2022年秋に急速に下落し1ドル=150円を超えた。当局の円買い介入もありその後少し落ち着きを見せたが、2023年9月から再び円安が進行し、1ドル=150円近くで推移している。日本円のあらゆる他通貨との為替レートの加重平均である名目実効為替レートも2021年秋から急降下を始め、各国との物価差を調整した実質為替レートの加重平均である実質実効為替レートは1970年の統計開始以来最低水準に落ち込んだ。円安には常に功罪両面があるが、日本経済全体にとっては円安の方が好ましい。日本が安くなるのは心情的には辛いが、円安は経済成長にとっては明らかにプラスである。輸入インフレが深刻にならない限り、円安是正策は必要無い。むしろ円安を好機と捉え、製造業は国内回帰を、観光関連業はインバウンドの更なる取り込みを図り、円安の恩恵の極大化に注力すべきである。
(1)円安傾向が続く可能性大
短期の為替レートの決定要因として最も重要なのは内外金利差である。例えば、日米金利差が5%あれば、理論的には毎年5%ずつ円安・ドル高が進んで初めて裁定する。日本の政策金利は依然マイナスであり、長期金利も1%未満である。片や米国の政策金利は5%を超えており、なかなか低下しそうもない。こうした状況では円安が継続しても不思議ではない。
長期の為替レートの決定要因として、内外物価水準の比が二国間の為替レート水準を決めるという購買力平価がある。国全体の物価水準を測る指標がないため、英Economist誌はビッグマックの価格を元に冗談半分で適正為替水準を示すが、ここではより信頼のおけるIIMA(国際通貨研究所)が算出する相対的購買力平価を観てみよう。IIMA算出の円/ドル購買力平価(2023年10月時点)は、企業物価で89円、消費者物価で108円である。いずれも実勢の150円よりかなり円高水準であり、ここからは長期的には何らかのきっかけで急速に円高に転ずる可能性を否定できない。しかし、購買力平価への調整がいつ起こるかは予見できないので、しばらくは内外金利差による円安が続くと観るのが常識的であろう。
(2)円安は安い日本をもたらすが実益は大
昨年秋に円安が進んだ際に盛んになった「悪い円安論」「円安亡国論」は、ナンセンスである。円安(円高)には、常にメリットもデメリットもあり、損得はセクターにより異なる。
円安のプラス面としては、まず輸出企業の収益拡大があげられる。特に外貨建て輸出については、円安が10%進めば円ベース売上高は10%増加する。輸出価格を下げる余地も生まれ、これは日本産品の輸出競争力を増し、輸出数量増加要因となる。
インバウンド(訪日外国人)増加による観光関連業等の収益増も大きい。国際収支上は、サービス貿易収支の改善となる。世界一の対外純資産残高を誇る日本にとっては、円安による所得受取(配当・利子等)の拡大も大きい。これも立派な日本の国民所得増加要因となる。
マイナス面としては、輸入物価上昇に伴う輸入インフレが有りうる。ただし、上昇した輸入価格を誰が負担するかは価格転嫁の状況次第である。輸入業者が価格上昇を転嫁しなければ輸入業者の利益が減少し、価格転嫁が進めば最終的には消費者が負担し、その際には消費者物価が上昇する。しかし、消費者物価上昇率は現状では3%程度であり、輸入インフレが発生しているとは言えない。
円安亡国論者は、日本のGDPの世界でのシェアや1人当たりGDPの世界ランキングの低下を強調する。これらは確かに日本人の溜息を誘うが、世界ランキングが低下して何か実害はあるのだろうか?また、円安により、海外での日本人の購買力が低下し、海外旅行をする日本人は高いランチやホテル代に閉口する。これは海外で活躍する国際派には大ダメージだろうが、一般の日本人にとっては海外旅行しなければ関係ない。日本企業の外国企業買収は難しくなるが、逆に外国からの対日直接投資は増加する。
新興国と異なり、日本は自国通貨の円で海外から資金調達できるため、通貨下落により対外債務の返済負担が増し通貨危機に陥る懸念もない。
円安は交易条件(円ベース輸出価格/円ベース輸入価格)を低下させるが、日本経済全体を考えれば交易条件悪化の負担は財・サービスの輸出数量増加で十分に補われるであろう。輸入インフレが深刻にならない限り、円高よりも円安の方が明らかに好ましい。だからこそ、昨年秋以降の円安・ドル高・ユーロ高の下で、日本経済は相対的に好調なのであろう。
(3)円安是正より円安を生かす産業構築が重要
具体的には、消費者物価上昇率が3%台後半に至れば、円安対応を考えるべきであろう。しかし、円安の是正策は、日本銀行の政策金利引き上げくらいしかない。物価上昇が著しい分野への補助金は、不公平を生み、価格機能を歪めるので好ましくない。当局による円買いドル売り介入も、一時的な効果しかない。また、あまり派手に介入すると、米国が為替操作と非難する恐れもある。
日本銀行が政策金利を0・5%にまで引き上げれば、おそらく円高トレンドが形成されるであろうが、当然国内経済に負担がかかる。債券保有者の損失も拡大し、金融システムの動揺を誘う懸念もある。そこまでのリスクを採りながら円安是正をするかどうかについては論議があろう。筆者は、以前からマイナス金利政策をやめて金融政策を正常化し、金利のある世界を取り戻すべきと主張してきたが、欧米のように金利を急速に引き上げるべきではないと考える。ましてや円安是正の為に利上げを行うことは本末転倒であろう。
逆にインフレが限定的であれば、円安は放置すべきであろう。むしろ、円安メリットを十分に享受することに注力すべきである。例えば、製造業は高まった国際競争力を元に国内回帰を進めるべきである。過去の円高期に海外に移した生産拠点を国内に移し、モノづくり日本を復活する好機である。また、日本の観光・飲食業及び関連運輸業等の訪日外国人への対応を強化する必要がある。増加するインバウンドに眉を顰(ひそ)めるのではなく、欧州諸国のように海外からの観光収入を一大産業に育てることにもっと力を入れるべきである。
2023年11月20日号 週刊「世界と日本」第2257号 より
世界の「超深海」へ挑戦
『江戸っ子1号』を支える首都圏の町工場
政策研究大学院大学
名誉教授
橋本 久義 氏

《はしもと ひさよし》
1945年福井県生まれ。69年東京大学工学部卒、通産省入省。78年~81年、JETRO調査員として西独に駐在。その後通産省機械情報局鋳鍛造品課長、中小企業技術課長、立地指導課長などを歴任。94年埼玉大学教授、97年政策研究大学院大学教授、2011年から現職。著書に『中小企業が滅びれば日本経済も滅びる』、『町工場こそ日本の宝』(共著)など多数。

東京都墨田区の下町にある赤、青、黄色を多用した二棟の建物。これが㈱浜野製作所だ。
小さな板金工場から、技術力と革新的なアイデアで急成長を遂げるばかりでなく、ものづくりベンチャーの援助をライフワークとして活動しているのが社長の浜野慶一さんだ。
同社は1968年に先代の浜野嘉彦氏が金型工場として設立したが、職人さん2、3人の零細企業だった。慶一氏は東海大学卒業後、修業のため別の町工場で働いていたが、93年父上が他界した後社長となった。
時はバブル崩壊期。苦難の船出であった。その時までは量産品の下請け生産をしていたが、受注はどんどん減っていく。このままでは海外勢に勝てないと、精密板金の分野に転身することを決意、大胆な設備投資をして、新規顧客獲得に乗り出した。一時は3億円近くの借金を抱えることになったが、顧客も拡大し、何とか軌道に乗せることに成功した。
しかし好事魔多し。2000年にもらい火で工場が全焼してしまう。その時の慶一さんの行動力がすばらしい。消防車が走り回っている最中に近所の不動産屋に駆け込み、「今燃えているのは私の工場です。そこにはお客様から預かった大事な半製品や、設備があります。鎮火したあと収容する場所が必要なのです」と頼みこみ、ウーウージャンジャン大騒ぎの最中に仮工場の賃貸契約を結んだという。おかげで火災による納期遅れも5~10日程度で済んだ。しかし設備も損傷を受け、仕事もままならない。頼みは失火賠償金だった。その交渉がまとまり、「○○日の午後に当社に受け取りに来てください」という当日の朝刊に、補償金を払ってくれるはずの会社が倒産したとの記事。
絶望の中で、仕事をこなす毎日だったが、バブル崩壊後の長期不況で、いよいよ行き詰まってしまった。最後まで残ってくれたたった一人の従業員に「残念だが、もう金がなくて、お給料も出せない。新たな就職先を探した方が君のためだ」といったところ、「社長、私は浜野慶一という人と一緒に働きたいからここにいるんです」という返事が返ってきたという。こういわせる魅力が慶一氏にはあったということだろう。
その後の鬼神も驚くほどの努力で何とか工場を維持してきたが、当時は日本経済絶不調。仕事がない。わずかながら発注される仕事を分析してみると、零細企業に発注される仕事は「めちゃくちゃ値段が安い」か「めちゃくちゃ難しい」か「信じられないほどの短納期」のどれかしかなかった。
値段が安い製品は、経営を圧迫する。難しい仕事はそもそもできない。しかし、「短納期の仕事」なら、寝ずにがんばればできるじゃないか!と、短納期にチャンスを見出し、「どんな特注品も翌日配達します」と宣伝をはじめた。
この、短納期戦略は見事に当たり、取引先が別の取引先を紹介するという具合で、3~4社だった取引先があっというまに数十社に増えた(今では千数百社にも上る)。今日発注・明日納品という厳しい納期でも喜んで引き受けた。従業員が夕方残業し、その後を浜野社長や常務が引き継いで仕上げ、明け方完成ということもしばしばあった。
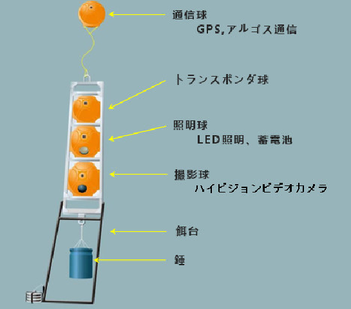
東大阪「まいど1号」計画に
触発されスタート
事業が順調に拡大していったのは交友関係の広さと、社長の好奇心にもある。
その成果の一つが深海探査機「江戸っ子1号」の開発だ。東大阪の町工場が作った人工衛星「まいど1号」が有名になったが、「大阪が宇宙なら、こちとらは海底で!!」と、首都圏の町工場が協力して深海探査機を開発した。これはガラスボールの中に、電源・照明・カメラ・記録装置等々をセットして、錘(おもり)で沈め、沈む過程で周辺を撮影し、電池が無くなったら、錘を切り離して海上に浮かび上がるので、回収して録画記録を調べるというもので、今まで日本海溝で8千メートル、マリアナ海溝1万2千メートルの3D動画撮影に成功している。AIで深海魚を追い、拡大撮影する機能もあるので、10メートル近い大型のダイオウイカなど、珍らしい深海生物の撮影に成功している。海洋研究開発機構(JAMSTEC)、芝浦工業大学、東京海洋大学等の支援も受けている。人間の乗る探査船は百億円近い費用がかかるが、この方式は数千万円のオーダーで実験可能である。
イノベーション拠点の開設
火事被災のどん底から今日の成功を築き上げた浜野社長の力には感心するが、それ以上に感心するのはその成果を後輩達の育成に注ぎ込んでいることだろう。その集大成として2014年にものづくりのためのイノベーション拠点となる「Garage Sumida(ガレージスミダ)」を開設した。社会課題の解決に情熱と気概を持って取り組むベンチャー達に、浜野製作所が保有する機械・工具を使わせ、場合によっては従業員が製造に協力するシステムだ。
Garage Sumidaがベンチャー企業や大企業から受けた新規事業の相談やプロジェクトの数は、これまでに300を超える。次世代型電動車椅子・パーソナルモビリティのWHILL、(ウィル=前輪が24個のタイヤで、階段等が上りやすい)を開発する「WHILL」、遠隔操作型分身ロボットOriHime(オリヒメ)開発の「オリィ研究所」、風力発電の「チャレナジー」等々夢が実現しつつある企業も多い。
夢を与え続ける企業として
浜野さんの志を物語るエピソードがある。「数年前、一本の電話が。『娘が車いす生活をしているのですが、自分の力で起きあがれるようなベッドに改造したい』その頃工場は大忙しでした。でも従業員たちは『社長、やりましょうよ!』と言うんです。そこで、引き受けて、手すりの位置を低くし、掴みやすいように、うねうねとした曲線型に改造しました。お届け後、『娘がものすごく喜んでくれました。本当にありがとうございました』と電話があり、従業員たちも喜んで、涙がでました」人情に厚い浜野社長の元気な声が響く浜野製作所は、顧客にも社会にも社員にも夢を与え続ける企業として発展し続けるだろう。
2023年9月4日・18日号 週刊「世界と日本」第2252・2253号 より
政局秋の陣 与野党の思惑は
「大きな政治」を目指すべき岸田首相
評論家
ノンフィクション作家
塩田 潮 氏

《しおた うしお》
1946年高知県生まれ。慶大法卒。雑誌編集者、月刊『文藝春秋』記者などを経て独立。『霞が関が震えた日』で講談社ノンフィクション賞受賞。『大いなる影法師』、『昭和の教祖 安岡正篤』、『田中角栄失脚』、『日本国憲法をつくった男 宰相幣原喜重郎』、『密談の戦後史』、『東京は燃えたか』、『内閣総理大臣の沖縄問題』、『危機の権力』、『解剖 日本維新の会』、近著に『大阪政治攻防50年』など著書多数。
9月2日、国民民主党の代表選挙で玉木雄一郎代表が前原誠司氏との一騎打ちを制して3選を遂げた。
野党第3党の党首選だが、政党政治の在り方と将来の与野党再編をめぐる路線が焦点となったため、注目を集めた。玉木氏は実行中の「提案重視・問題解決型」の現実路線を主張した。前原氏も持論の「与党と対峙する非自民・非共産の野党結集」を訴えた。
前原氏は昨年11月、インタビューで「このままでは国民民主党は消えてなくなると思う。どこかで何らかのアクションを取らなければ」と明かしたが、決意を実行したのだろう。「低迷の与党」対「躍進する日本維新の会」という構図が明確になってきたのを見て、アクションを起こす時機と判断したに違いない。
実際に今、自民党による国民民主党の取り込みや、維新を軸とする野党結集構想が飛び交っている。玉木氏と前原氏の一戦は、与野党各党の思惑の投影という側面があった。
現在、自民党は衆議院で単独で過半数を超えているが、参議院は過半数に8議席、足りない。公明党との連立は衆参ねじれの回避が最大の目的だが、参議院13議席の国民民主党で8人以上が与党入りすれば、自公連立でなくても、自民党はねじれを阻止できる。
今年の前半、衆議院での選挙協力をめぐって「自公の亀裂」が表面化した。岸田文雄首相は6月、解散・総選挙を企図して、「解散不発」という失敗を演じたが、その主因は自公対立であった。自公連携は10月で24年となるが、両党とも「強まる分断への遠心力」に対する危機感は強い。
一方、岸田内閣は「解散できない首相」のマイナスイメージや物価高騰、マイナンバーカード問題などが響いて、再び支持率低落に見舞われた。8月の調査で読売新聞は政権発足後の最低の35%、時事通信は2番目の低率の26・6%と低迷中だ。
首相の政権戦略は、来年9月の自民党総裁任期満了時の総裁再選が最優先課題である。首相はその前の衆院選実施・勝利による再選確実の状況作りを狙った。解散意欲は本物で、次の「政局秋の陣」では、まず内閣改造と自民党役員人事で総裁再選の布陣を用意し、10〜12月に解散再挑戦というシナリオを想定していたはずである。
ところが、支持率再下落で、解散ムードは吹き飛んだ。首相も党内のライバル不在という現状を見て、「衆院選なし」でも続投可能と判断し、総裁選後への衆院選先送りに傾斜するのではという見方が有力となっている。
他方、安倍晋三元首相の国葬実施や日本銀行総裁人事、G7広島サミット(主要国首脳会議)へのウクライナ大統領招待など、意外にも「サプライズ大好き」の岸田首相は、断固、今秋の衆院選実施に踏み切るかも、という見立てもある。
その反面、今年12月で与党11年となる自民党が、「1強」にもかかわらず、ここ数年、衰弱の下り坂にあるという指摘も見逃すことができない。大きな要因は支持基盤の融解という実態である。
固体が液体に変わることを融解というが、自民党に限らず、維新を除く従来型の各党は支持基盤の融解現象に直面していると映る。政党支持の固体は、自民党では各業界や全国各地の各種団体などの既得利益構造、立憲民主党と国民民主党は労働組合、公明党は創価学会、共産党は伝統的な左翼勢力だが、いずれも液状化が激しい。
経済成長の終焉(しゅうえん)、急激な国際化やIT社会到来、少子・高齢化などによる社会構造の変化と国民の価値観の多様化などが原因だ。
「自公の亀裂」も、維新に対抗する選挙対策をめぐる思惑と計算の狂いという問題だけではない。自公連立はもともと「氷上のダンス」で、その現実が露呈したという深刻な事情が潜んでいる。
自公連立の内実は、愛を失った24年の結婚歴の夫婦が氷上でダンスを踊っているような危うさと背中合わせだ。両党にとって権力による果実が「厚い氷」のときは問題ないが、融解現象で足もとの氷が薄くなると、割れ目が拡大して湖水に沈没という「薄氷の連立」の一面が顕在化する。
下り坂の自民党を再び上り坂に変えるには、何が必要か。何よりも岸田首相が国民の「大きな民意」をくみ取り、当面の課題処理だけでなく、日本再生の将来像、立国の基本路線、シナリオなどを明確に提示して挑戦する「大きな政治」を目指すべきである。
その姿勢と意欲が見えなければ、国民の中に潜在する「政権交代可能な政党政治」復活への期待が高まる。民意が強く望めば、与野党再編や野党結集の歯車が再び動き始める。冒頭で触れた国民民主党代表選は、実はその序幕だったという展開になるかもしれない。
自民党が下り坂のまま、再浮上できなければ、十数年ぶりに政権交代劇の幕が開くことになる。正念場となる決戦の時期はいつか。
大胆に予想すると、決戦は2025年と見る。25年は6〜7月に次期参院選があり、衆院選がない場合の衆議院議員の任期満了が10月30日に訪れる。岸田政権が続いているかどうかは分からないが、自民党が下り坂で解散・総選挙を先送りし続けると、25年夏の衆参同日選挙実施論も噴出しそうだ。
決戦の鍵は主権者である国民が握っている。どの政治勢力に将来を託すのか、勝負は約2年の長丁場となるが、政治の側も、国民の関心が高い課題や目標を論点として提示しなければならない。続投中なら、そのとき、岸田首相は就任時からおそらく唯一、唱え続けている「憲法改正」を掲げて衆参同日選を仕組むのだろうか。
同時に、25年は維新が推進してきた関西・大阪万博の開催年だ。今は快進撃の維新だが、馬場伸幸代表は足もとの疑惑で「文春砲」の直撃を受け、並行して万博開催準備の遅れや不手際の問題も抱えて、党代表として指導力が問われている。
本番の25年、維新は政権交代劇の見せ場で主役を演じることができるかどうか。もしかすると、万博を境に一気に凋落(ちょうらく)という大苦戦も、ないとはいえない。
2023年9月4日・18日号 週刊「世界と日本」第2252・2253号 より
これからの経済・景気の展望
~米中経済の悪化で鈍化も、国内景気回復持続~
第一生命経済研究所 経済調査部
主席エコノミスト
永濱 利廣 氏

《ながはま としひろ》
95年早稲田大学理工学部卒業後、第一生命入社。05年東京大学大学院経済学研究科修士課程修了、16年より現職。跡見学園女子大学非常勤講師兼務。内閣府経済財政諮問会議有識者、経産省物価高における流通業のあり方検討会委員、総務省消費統計研究会委員、景気循環学会常務理事。著作に「給料が安いのは円安のせいですか」(PHP研究所)等。
23年度後半の世界経済の動向
(1)世界のインフレ率動向
世界の消費者物価は国際商品市況の落ち着きやこれまでの金融引き締めを背景に、財価格の下落を主導に米国→欧州→日本の順番に急速に伸びが鈍化してきた。特に米国では、住宅価格下落が住居費などのサービスインフレも低下に転じており、ユーロ圏ではエネルギー供給制約がある中でも、エネルギー確保のため需給両面で取り組みを実施したことから、米国に追随してインフレが低下してきた。こうした中、よりコストプッシュの要素が大きい日本のインフレ率は、価格転嫁の遅れによりインフレ率の低下が最も遅れており、国内需給のタイト化や賃金上昇による内生的な物価上昇とはなっていない。
(2)世界の金融政策動向
インフレ率のピークアウトに伴い、欧米では金利と量の双方から金融引き締めのペースが鈍化している。ただ、追加の利上げ観測がまだ燻(くすぶ)っていることから、長期金利は昨年ピークに近い水準まで上昇している。
ただ、米国では住宅需要の軟化から住宅価格が下落していることからすれば、既に政策金利は上限近くまで来ており、年度後半以降もディスインフレが継続することで、FRB(米国連邦制度理事会)は当面政策金利を据え置こう。
一方のユーロ圏のほうも、米国よりもインフレ率低下が遅れるものの、既に政策金利が中立金利を上回っているため、ECB(欧州中央銀行)も当面金融政策は据え置きで、来年後半以降は利下げに転じるだろう。
こうした中で日銀は、7月に指値オペの金利水準を0・5%から1・0%に引き上げることでYCC(イールドカーブ・コントロール・長短金利操作付き・量的質的金融緩和)の修正を行ったため、当面修正の可能性は低いだろう。仮にYCC撤廃やマイナス金利解除に動くとすれば、景気回復の持続により来年春闘で賃上げの継続が確認される来年度以降になろう。
(3)23年度後半以降の海外景気
2023年度前半にかけての世界経済は、金融引き締めによる下押しがある一方で、ユーロ圏以外の主要先進国はいずれも総合PMI(企業の購買担当者景気指数)が50を上回って推移するなど、総じてみれば底堅い動きがみられた。
背景には、雇用が安定する中での物価高対策や、特に日中において経済活動の再開に伴うサービス消費、GX(グリーントランスフォーメーション)・DX(デジタルトランスフォーメーション)・レジリエンス強化面を中心とした設備投資の増加がある。
特に米国では、堅調な雇用情勢を受けて労働需給の引き締まりが続き、人手不足により高い賃金上昇が継続したことで個人消費や輸出がけん引役となってきた。しかし、これまでの急速な金融引き締めを受けて住宅ローン金利は急上昇しており、今後もこれまでの利上げの影響が見込まれる中、住宅市場や設備投資の悪化が主導することで、年度後半の米国経済は明確に減速局面に入ろう。ただ、労働市場の勢いが下支えすることで、景気後退にまで至る可能性は低いと想定される。
一方、足元で悪化が目立つユーロ圏の景気だが、雇用の改善が続く中で最悪期は脱しつつあると見る。今後はインフレ鈍化に伴う消費の下押し緩和、エネルギーの供給制約や価格高騰の緩和に伴う生産活動の回復により、来年にかけて幾分景気は持ち直すと見る。
こうした中、デフレリスクが高まる中で政府の対応が鈍い中国経済が最大の懸念材料となろう。昨年末のゼロコロナ解除で一時的に持ち直しの動きがあったものの、不動産市況の悪化や地政学的緊張の高まりによる悪影響が当初の予想以上に重しになっている。特にGDPの3割相当を占めるとされる不動産開発部門は低調が続いており、企業の債務問題が長期化する中で、不動産開発投資が足を引っ張っている。これを受けて中国人民銀行も金融緩和に着手しているが、地政学的緊張の高まりによる中国からの資本流出につながるリスクもジレンマとなっている。こうした中で、特にコロナ禍以降に少子化に拍車がかかっており、中国の経済成長率は長期的にも伸びが抑制される可能性が高まっている。

(4)23年度後半以降の国内景気
このように、すでにPMIで減速の可能性を示している世界経済は、来年にかけてリセッションは避けられるものの、米中中心に減速が不可避となろう。
こうした中で、肝心の日本の景気は相対的に底堅い回復が予想される。背景には、コロナからのリオープンを原動力としたサービス消費の回復、政府の支援策の恩恵も受けたGX・DX・レジリエンス強化向けの設備投資、中国人の日本向け団体旅行解禁を受けてのインバウンド消費の更なる拡大がある。
なお、当面のリスクは財消費の抑制要因となっているコストプッシュインフレの影響に加え、世界経済の減速による輸出や生産・設備投資への悪影響だが、世界的には依然として日本の主力産業である自動車の繰越需要が旺盛なため、景気の腰折れは避けられると見る。
以上より、今年度後半以降の国内景気は、海外経済の悪化を受けて減速を余儀なくされるものの、底堅い国内のサービス消費や設備投資、インバウンド消費や自動車関連輸出が下支えとなることで、緩やかな回復を続けると予想する。
2023年8月7日号 週刊「世界と日本」第2250号 より
日米同盟と核抑止を考察する
評論家
江崎 道朗 氏

《えざき みちお》
1962年、東京都生まれ。九州大学卒業後、国会議員政策スタッフなどを経て2016年夏から評論活動を開始。主な研究テーマは近現代史、外交・安全保障、インテリジェンスなど。産経新聞「正論」執筆メンバー。2020年、フジサンケイグループ第20回正論新風賞を受賞。最新刊に『なぜこれを知らないと日本の未来が見抜けないのか』(KADOKAWA)。
核兵器の必要性を認めた「核軍縮に関するG7首脳広島ビジョン」
5月19日、広島G7(先進7カ国)サミットにおいて「核軍縮に関するG7首脳広島ビジョン」が公表された。マスコミ報道を見て、今回もまた「核なき平和」みたいな美辞麗句を述べたと誤解している人が多いようだ。だが、「広島ビジョン」を実際に読んでみると、意外なことに気づく。実は「核を無くせ」ではなく、「核は必要だ」と言っているのだ。
「広島ビジョン」では、ロシアによる核の恫喝(どうかつ)をこう非難している。
《我々は、ロシアのウクライナ侵略の文脈における、ロシアによる核兵器の使用の威嚇、ましてやロシアによる核兵器のいかなる使用も許されないとの我々の立場を改めて表明する》
そして、ロシアによる核恫喝に対抗するためにも、自国の防衛のために核兵器が有効であるとして、次のように記されている。
《我々の安全保障政策は、核兵器は、それが存在する限りにおいて、防衛目的のために役割を果たし、侵略を抑止し、並びに戦争及び威圧を防止すべきとの理解に基づいている》
要は核の恫喝を厭(いと)わないロシアと中国などを念頭に、《法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を守り抜く》ことを話し合い、自由主義陣営の核兵器が防衛目的の役割を果たしていることを確認したのが、今回の広島G7サミットだったわけだ。
とはいえ、北朝鮮や中国が、日本に対して核の恫喝を仕掛けてきたとき、米国は本当に対抗してくれるのか。日本は戦後長らく核兵器については思考停止状態で、「いざとなれば米国が何とかしてくれる」かのような根拠なき楽観論に逃げ込んでいた。
核に関する日米拡大抑止協議(EDD)
だが、北朝鮮の核開発の進展を受けて日米両国は2010年、日米同盟の中核である拡大抑止の維持・強化のあり方を議論するための恒常的な場として日米拡大抑止協議(EDD)を始めた。
今回も広島サミットを受けて6月26日から27日まで日米両政府は、米国ミズーリ州ホワイトマン空軍基地において日米拡大抑止協議を実施した。外務・防衛当局が出席し、核使用への抑止に一層備えるために情報共有、訓練及び机上演習などについて議論し、実際に机上演習も実施した。
加えて岸田文雄政権は、バイデン政権に対してアメリカの核の傘というが実際に使われる核兵器とその運搬手段はどうなっているのか、この目で確認させて欲しいと求め、日本の代表団が今回、B2ステルス戦略爆撃機や退役した大陸間弾道ミサイル「ミニットマン2」の発射管制センターの視察を行っている。
この拡大抑止協議をさらに実のあるものにするためには、日本政府としてしなければならないことがある。それは「日本独自の核抑止戦略」を策定することだ。
北朝鮮の核兵器、ミサイル技術の進展は目覚ましく、いずれ日本も核による恫喝を受けることになる。その時点でアメリカによる核攻撃の準備を依頼するのか、それとも日本本土が核攻撃を受けた際に報復を依頼するのか、その際、アメリカはどの核兵器をどのように使うのか、その攻撃場所はどこなのか。
これは中国の場合も同様だ。台湾紛争に際して在日米軍の使用を米軍に認めないよう中国は当然、圧力を加えてくるだろうが、日本が核の恫喝を受けた場合に、アメリカはどのような対抗措置をとるのかなど、具体的なシミュレーションに基づいて「米国に対する日本の要望」を細かく決定し、米国と事前に話を詰めておかないといけない。
まずは、日本独自の「核抑止戦略」の策定を
要は、日本独自の戦略がないまま日米で協議を続けたところで、「アメリカさん、とにかく何とかしてください」という話にしかならないのだ。
そう考えた自民党保守系の「日本の尊厳と国益を護る会」(青山繁晴代表、山田宏幹事長)が、広島G7サミット直前の5月18日、松野博一官房長官と国会内で面会し、岸田首相宛ての提言「核抑止戦略に関する提言」を手渡した。
「日本独自の核抑止戦略」を策定するためには、官邸の国家安全保障会議において核に関する議論を開始しなければならない。そのたたき台を「護る会」は作成し、政府に提示したわけだ。
提言では冒頭、以下のような趣旨を述べている。
《「護る会」では、我が国の平和と安全のためには、核抑止についての議論は避けてはならない重要な課題であり、核問題を自分自身の国家安全保障の問題として考える時期に来ているとの問題意識のもと、令和4年11月から令和5年3月まで4回にわたり有識者を交えて核抑止についての勉強会を重ねて来た。そこで行われた議論を踏まえ、我が国としての「核抑止戦略」について考えるべき論点と今後の安全保障に関する政策への提言を取りまとめたところである。今我々は「タブー無き核抑止」を議論し、現実の政策、戦略として具体化することが求められている。
なお、憲法をはじめ我が国として在るべき方向性を今後の課題として不断に検討することは当然であるが、本提言においては、「日米安全保障条約」に基づく日米同盟関係の維持、「核拡散防止条約(NPT)」に基づく権利・義務の堅持など、これまでの我が国の基本政策は現実的なものであるべきとの基本姿勢に立脚している。》
わが国はいま核の脅威に直面しているわけだが、だからと言って「核武装せよ」といった極論を述べても、現実の政治は動かない。大事なことは、核の脅威にどう立ち向かうのか、日本としての戦略をまず持とうではないか、というのが護る会の提言の根幹だ。
そして日本が独自の核抑止戦略を策定することは、現行憲法や日米安保条約、NPT体制のもとでも可能なことなのだ。
せっかく広島G7サミットで、防衛目的のために核兵器は必要だと確認したのだ。
ロシア、中国、北朝鮮の「核の脅威」から日本の平和を守るためにどうしたらいいのか、できるだけ早く日本独自の「核抑止戦略」を策定するよう、政府に求めたいものである。
2023年8月7日号 週刊「世界と日本」第2250号 より
ChatGPTとどう向き合うか
千葉商科大学
国際教養学部准教授
常見 陽平 氏

《つねみ ようへい》
1974年生まれ。北海道出身。一橋大学商学部卒業。同大学大学院社会学研究科修士課程修了。㈱リクルート、コンサルティング会社等を経てフリーに。雇用・労働、キャリア、若者論などをテーマに執筆、講演に活躍中。千葉商科大学国際教養学部専任講師を経て現職。
AIと人間の共存についての議論は特にこの10年間、盛り上がっている。AIが人間の雇用を奪う論、人間を支配する論、あらゆるデータが流出するリスク、AIとの役割分担をめぐる倫理的問題などが議論されてきた。
一方で、AIの進化は止まらない。利用事例は増え続け、その度にAIは学習していく。是非を議論しているうちに、気づけばAIに囲まれている。スマートフォンを使っている限り、逃げられない。いや、私はスマホを持たないと主張する人も、気づけば暮らしの隅々にAIが広がり、いつの間にか取り囲まれている。
今回、生成AI、対話型AIのChatGPTが世界を震撼させたが、これは物語にたとえると、序章ではないが、前編の第3章くらいだと見ている。今後も変化は継続して起こり、その度に同じような議論が巻き起こるだろう。AIが人間を上回るのは何年後かという未来予測もよく発表される。事実をもとに推測する地道な努力をリスペクトしつつ、とはいえ、今回のChatGPTのように想像をはるかに上回る新技術、新サービスが登場する可能性も否定できない。
2023年は日本の大学にとって慌ただしい年となった。まだ約5カ月残っているのだが、そう断言できる。大学の募集停止のニュースが相次いだ。今後、18歳人口が減少し続けることから危機感が高まっている。生き残りをかけた取り組みも日々、報じられる。しかし、なんといってもChatGPTである。教育、研究を行う大学としてどう対応するのかが話題となった。
東京大学を始め、各大学で声明やガイドラインが発表された。言うまでもなく、レポート執筆などにおいての悪用が懸念された。
大学において、このAIが関係するのは学生だけではない。教員も活用する。研究支援、教育支援、ユーザーサポート、コラボレーションなどだ。なお、この4つの活用例は、私がChatGPTに「東京大学はChatGPTをどのように活用するか?」と質問した答をまとめたものである。
大学は必ずしも使用を禁止したわけではない。むしろ、活用をしつつ学ぶことを推奨する大学も現れている。
問題は、AIを活用することの是非だけでなく、「どのように使いこなすか」が論点となる。青学、慶応、東経、東洋、日本という私立大学のゼミに属する学生が100名集まる研究発表会で、ChatGPTの利用状況について質問してみた。「使ったことがある」という学生は9割程度だった。高い認知度、浸透度と言っていい。一方で「週に1回以上使っている」つまり、使い続けている人はどれだけいるか確認したところ、2割弱もいなかった。「レポートに使ったことがあるか?」と質問したところ、教員たちが見ている前で手をあげた学生が1名だけいた。限られたサンプルではあるが、有名大学の感度の高い学生たちはもちろん、生成AIを知っているし、使ったことはあるが、有効な利用法が分からず、利用をやめてしまっている。
大学生に関していうと。就職活動への利活用も想定される。現にこれを活用したエントリーシート支援ツールもすでに登場し、全国紙などで紹介された。採用担当者の間では、「もう、直接、学生に会って確認するしかない」というため息も漏れる。
一方、就職活動・採用活動の現場では既にAIやデータの利活用が進んでいる。大学生が就職活動で業界・企業研究やエントリーに活用する就職ナビにはもう10年以上前からこれらが導入されており、本人の属性やクリック履歴に基づいた、マッチング率が高そうな検索結果が表示される。
2010年代後半には内定者の辞退率を予測するサービスが、個人情報の取り扱いをめぐって問題となった。ただ、賛否、是非は別として、このようなサービスが既に世の中に存在することは確認しておきたい。
さらに、AIが書類選考や面接を担うサービスも既に登場し、選考に活用されている。大量のエントリーシートをAIがかわりに読み込み、合否を判断するのだ。
このような話をすると、「AIが人を判断していいのか?」という疑問が起こる。この問いは、その是非をめぐるものと、AIに本当に判断できるのかという疑念などに分解される。ただ、後者に関してはブーメランが待っている。「そもそも人間は、正確に物事を判断するのか」という問いだ。大量のエントリーシートを読み込ことは苦痛だ。処理しきれないがゆえに、学生は大学名でふるいにかけられ「学歴フィルター」の餌食となる。採用担当者は人事の中でも入れ替わりが激しいポジションだ。経験が蓄積されるわけではない。AIは経験を蓄積し、学び続ける。この問いを重ねると「AIが判断することの是非」の議論から発展し、そもそも「人間が判断していたことの是非」が問われることになる。
リクルートグループの経営者は、「1クリックで就職・転職が可能な社会を実現する」と宣言している。賛否、是非は別として、あくまでサービス設計やテクノロジーの上では実現可能性は高そうだ。
私たちに今、できることは何か。それは人間が取り組むべき仕事、AIにまかせてはいけない仕事とは何かを考え続けることではないか。
常に自分の仕事について、これは人間がやるべきなのか、AIに任せるべきなのかを胸に手をあてて、考えたい。単純作業だけではない。ときに考えることが必要な仕事も、AIに任せてみる。最終的に決定する立場をいかに人間が果たすか。これを考えたい。人間が取り組む仕事がより明確になる。
もちろん、いまやコンテンツなどクリエイティブなものもAIがつくってしまう時代である。人間とは何かが常に問われ続ける。ただ、AIは最適化に向いているのであって、規格外のモノやコトを創ることに向いているようには思えない。もちろん、この規格から外れたモノやコトをAIがつくり出す時代がすぐそこにあるとも言えるが。人間の感情、アナログであることこそ、AIの苦手なことではないか。
人間が人間らしくいられるにはどうするか。AIの進化、変化を見つめつつ、考えたい。会社員時代、明らかに採用ミスと上司たちから叱られた若者が企業を背負って立つ人材に成長したこと、誤字脱字のある文章をSNSに投稿したところ凄まじく拡散したこと、これは好き嫌い、良い悪いは別として、極めて人間らしいことだと思っている。それもAIが学んでしまうかもしれないのだけれども。
バックナンバーはこちら













